〇01/08 15:00~17:00 入試説明会 キャンパスプラザ京都第4講義室(京都駅前)
〇01/11 15:00~17:00 入試説明会 立命館アカデメイア@大阪(淀屋橋駅前)
島ビル6F 06-6201-3610
京阪・地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅下車 京阪14-B出口 エスカレーター上すぐ
〇01/17 18:00~20:00 入試説明会 びわこ・くさつキャンパスアドセミナリオ208号
〇01/20 18:00~20:00 入試説明会 衣笠キャンパス 存心館805号
◆01/29 「争点としての生命」研究会 http://www.arsvi.com/0u/02.htm
◇02/26 渡辺 公三『司法的同一性の誕生──市民社会における個体識別と登録』,言叢社,461+27p. 3800
◆02/27 「争点としての生命」研究会 http://www.arsvi.com/0u/02.htm
〇02/28 合格発表
◇03/01 西 成彦・原 毅彦 編『複数の沖縄──ディアスポラから希望へ』,人文書院,437p. 3500
◇03/25 小泉 義之『レヴィナス──何のために生きるのか』,日本放送出版協会,109p. 1000
〇04/01 入学式
〇04/02 ガイダンス
〇04/15 大学院進学説明会(本学在籍者対象)
◆04/19 セン理論に関する学際的研究 第1回
◇04/23 西川 長夫・大空 博・姫岡 とし子・夏 剛 編『グローバル化を読み解く88のキーワード』,平凡社,294p. 2000
◇04/26 共生と多様:普遍性研究会
新原道信氏(中央大学文学部)「痛みとともにあるひと(homines patientes)と聴くことの社会学」
◇04/26 〈複数文化研究会〉第37回例会
☆出版記念コロキウム—-『複数の沖縄』をめぐって
http://www.arsvi.com/0a/f01.htm
◇04/27 オーラルヒストリーの会・第1回研究会
http://www.arsvi.com/0a/o02.htm
◆05/02 セン理論に関する学際的研究 第2回
◆05/03 公共研究会 講師:山森亮氏
◆05/15 『生命理論』1・2合評研究会
◇05/17 北村 健太郎「「神聖な義務」をめぐって」(報告)
2003年日本保健医療社会学会大会 於:龍谷大学・大宮学舎
http://square.umin.ac.jp/medsocio/
◇05/18 松原 洋子「医療技術と生命倫理」(講演)
新生児聴覚スクリーニング検査を考えるシンポジウム
http://www.arsvi.com/0d/h2003.htm
◇05/30 小泉 義之『生殖の哲学』 河出書房新社,126p. \1500
◆06/02 シンポジウム「21世紀の公共性に向けて――セン理論の理論的・実践的展開」
〇06/08 入試(第1回・学内進学者対象)
◇06/10 渡辺 公三 20030610 『レヴィ=ストロース──構造』,講談社,現代思想の冒険者たち Select,342p. 1500
◇06/18 Wiseman監督作品のビデオ上映会
2:40~High School(清心館457)4:20~Welfare(清心館458)
◇06/25 Wiseman監督作品のビデオ上映会
2:40~Zoo(清心館457)4:20~Zoo(続き)(清心館458)
◇06/25 国際学術交流研究会「フランスとヨーロッパにおける移民の新しい形態」
http://www.arsvi.com/0u/r0103.htm
フランス社会科学高等研究院 教授 Herve Le Bras
コメンテーター:西川長夫
◇07/02 Wiseman監督作品のビデオ上映会
未定
◆07/08火 フレデリック・ワイズマン作品ビデオ上映会
◆07/11金 西川科研第1回研究会
高橋秀寿「ヒロシマと戦後国民国家──平和記念公園の比較研究」
〇07/13日 入試説明会 小泉・西(予定) 於:衣笠
◆07/15火 フレデリック・ワイズマン作品ビデオ上映会
◆07/16水 フレデリック・ワイズマン作品ビデオ上映会
◆07/17木 「争点としての生命」研究会
加藤和人氏「ゲノム研究の今を考える──ビジネスか哲学か」
◆07/22火 フレデリック・ワイズマン作品ビデオ上映会
〇07/26土 入試説明会 渡辺・立岩 於:大阪
〇07/29火 博士予備論文構想発表会
◇08/02土 西成彦「「不条理文学」再読──カフカとカミュ」
立命館大学土曜講座 14時~16時 立命館大学末川会館1階ホール
◇08/17日 レクチャー・シンポジウム:「証言とその奥行き/モノと人間の狭間で言葉は…」
http://www.arsvi.com/2000/030801.htm
西成彦他
◆08/29金 松原科研・研究会
古井透「リハビリ再考──「がんばり」への呪縛とそのOUTCOME」
〇09/03水~09/10水 10月入試出願期間
cf.http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/in/
◆09/20土~21日 「生命科学・生命技術の進展に対応した理論と倫理と科学技術社会論の開発研究」(科研費・代表・小泉義之・立命館大学)9月研究会
◆09/23火~25木 キムリッカ編The rights of minority culutures講読会
14:00~ 学而館2階・先端研「生命」院生室
お問合せは院生の佐藤さんへnana@rossberg.net
→紹介をホームページに掲載
〇10/04土 入学試験
◇10/13祝 小泉義之「社会性と生物性」(報告)
第76回日本社会学会大会・シンボジウム 於:中央大学
報告要旨(2003/07提出)/報告原稿
◇10/13祝 北村健太郎「「神聖な義務」論争をめぐって」(報告)
第76回日本社会学会大会 於:中央大学 報告要旨
配付資料/報告原稿http://www.ritsumei.ac.jp/kic/~gr018035/jss03.htm
◆10/18土~11/03土 フレデリック・ワイズマン ドキュメンタリー・プロジェクト
cf.Wiseman, Frederick
◇20031101 『現代思想』31-13(2003-11) 1238+税=1300
特集:争点としての生命
http://www.arsvi.com/0m/gs2003.htm
http://www.seidosha.co.jp/siso/200311/
◇金森 修+松原 洋子 20031101 「生命にとって技術とは何か」(討議)
『現代思想』31-13(2003-11):026-043
◇立岩 真也 20031101 「現代史へ──勧誘のための試論」 資料
『現代思想』31-13(2003-11):044-075
◇小泉 義之 20031101 「受肉の善用のための知識――生命倫理批判序説」
『現代思想』31-13(2003-11):076-085
◇松原 洋子 20031101 「「新遺伝学」における公と私」
『現代思想』31-13(2003-11):086-092
◇大谷 いづみ 20031101 「「いのちの教育」に隠されてしまうこと──「尊厳死」言説をめぐって」
『現代思想』31-13(2003-11):180-197
◇11/15土 横田陽子「日本におけるSARSへの対応 「スーパースプレッダー」──専門領域から一般社会へ」(報告)
科学技術社会論学会 2003年度年次研究大会 2003年11月15-16日 於:神戸大学
http://homepage2.nifty.com/tsukaken/kobesinpo/2nd_sts_aso/program.htm
報告要旨
◆11/22土 アイリス・ヤング勉強会
◆11/21金 西川科研・第2回研究会
ノア・マコーマック「都市の近代化と分断──明治期の下層社会の場合」
16時30分~ 立命館大学衣笠キャンパス・創思館4階 共同研究会室403
◆11/22土 アイリス・ヤング集中講義・事前勉強会・第1回
◆11/29土 入試説明会 於:琵琶湖草津キャンパス
◆12/06土 入試説明会 於:衣笠キャンパス
◆12/07日~立命館大学大学院先端総合学術研究科開設記念
公開講演会/公開研究会「知の潮流を創る パート3 」
◆12/07日 2003年度生物学史総会・シンポジウム
「生物進化論と創造論の対立―米国における科学と宗教の現在―」
◆12/15月 アイリス・ヤング集中講義・事前勉強会・第2回
◆12/17水 立命館大学大学院先端総合学術研究科開設記念
公開講演会/公開研究会「知の潮流を創る パート3 」第2回
◆12/19金 西川科研第3回研究会
石原俊「ジョン・万次郎における法と身体」
16時30分~ 立命館大学衣笠キャンパス・創思館・共同研究会室403
◆12/20土 入試説明会 於:大阪
◆12/26金 西川科研第4回研究会
&公開講演会/公開研究会「知の潮流を創る パート3 」第3回
吉見俊哉「戦後・空間」
14時~ プロジェクト研究会室303・304
◆12/26金~12/27土 渡辺科研研究会
◇12/29月 英語ページ掲載(トップページ+メッセージ+各プロジェクト紹介)
◇12/30 神林 恒道・仲間 裕子 編 20031220 『美術史をつくった女性たち──モダニズムの歩みのなかで』,勁草書房,238+12p. 3000
『コアエシックス』発刊にあたって
立命館大学大学院先端総合学術研究科の紀要としてこの『コアエシックス』が刊行されることになった。院生、教員そして関係者の皆さんとともに喜び、また、この出発を祝福し、今後の発展を祈りたい。
本研究科は2003年4月に発足した。そして2004年度のほぼ1年をかけてこの紀要の刊行を準備し2005年3月の発刊に漕ぎつけた。新しい研究科にふさわしく、紀要の編集方針についても、かなり細かな部分に至るまで教授会や編集委員会での、議論の対象となった。時には必要以上に枝葉末節に至る議論に時間を費やし過ぎたかもしれない。
それは、研究科長のリーダーシップの欠如という面も否めないにせよ、編集委員会を構成した教授会メンバーの全員が、自前の媒体を創り出すことに示した熱意の現われだった。院生たちにとってきちんと外部の評価を与えられた発表の場を創出し提供すること、これがすべての議論の大前提だった。この大前提がどのように達成されるかは、今後の院生諸君の紀要の活用にかかっている。研究科発足後、1年の準備期間をとった理由は、開設の作業と紀要創刊の作業を並行しておこなうことの難しさを避けたということ以上に、2年度めの後半に「博士予備論文」(区分制大学院での修士論文に相当)の準備が本格化する時点で刊行することを当初から予定していたからである。また、紀要に少し先立って「コアエシックス叢書」第1冊とも呼ぶべき『生命の臨界―争点としての生命』(人文書院)も大学の援助を得て刊行された。検討中の続巻とともに、プロジェクト研究の成果刊行を中心としたいわば紀要の姉妹編とも呼べるものなので紹介しておきたい。
刊行準備に当たっては研究科、学会の紀要の編集刊行の経験豊かな松原教授が中心的な役割を果たしてくださった。また編集実務には4名の助手の皆さんが携わってくれた。多様な領域にわたり表現や書式の異なった論文の編集作業はこみいったものとなる。この難しい仕事に取り組み、今後のための範となる第1号の刊行を首尾よく果たしてくださった皆さんに感謝したい。
2005年3月
立命館大学大学院
先端総合学術研究科
渡辺 公三
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.7 2011年

◇目次 PDF<308KB>
論文
生体肝移植をめぐる移植後の家族変容―ドナーインタビューの分析より―
一宮 茂子p.1
PDF<387KB>
「認められない」病いの社会的承認を目指して
―韓国CRPS患友会の軌跡―
大野 真由子p.11
PDF<550KB>
注意の二重性―映画とヴィデオゲームのスクリーンの考察から―
越智 朝芳p.23
PDF<409KB>
ビデオゲームソフトウェア付属マニュアルの内容分析的研究
―「物語設定」を対象とした調査と考察―
尾鼻 崇p.35
PDF<635KB>
滋賀難病連運動の困難期
―滋賀腎協の離脱と滋賀県行政との対立―
葛城 貞三 p.51
PDF<392KB>
国際開発援助からみた女性障害者
―障害者権利条約における女性障害者の主流化が開発援助にあたえる意義と課題―
金澤 真実 p.63
PDF<352KB>
純情漫画のコマ割り演出における歴史的変化についての考察
金 素媛 p.75
出来事の否認に抗う
―パレスチナ人の「ナクバ」の語りの挑戦―
金城 美幸 p.89
PDF<375KB>
高等女学校の美育からみる「少女」と化粧の関係
小出 治都子 p.99
PDF<433KB>
高齢者社会的孤立問題の分析視座
小辻 寿規 p.109
PDF<433KB>
孤独死報道の歴史
小辻 寿規・小林 宗之 p.121
PDF<456KB>
手話通訳事業の構造的課題に関する考察
―金沢市・京都市・中野区の調査から―
坂本 徳仁・佐藤 浩子・渡邉 あい子 p.131
PDF<417KB>
近代日本美術史論考に見る「桃山」概念の成立と変遷
ダニエル・サストレ・デ・ラ・ベガ p.141
PDF<457KB>
医療的ケアを必要とする子どもの地域生活支援のあり方
―親の自主グループづくりから考察する―
佐藤 浩子 p.153
PDF<375KB>
運動によって勝ち取られた、正規職員が担うべき社会福祉としての家庭奉仕員労働
―1960年代後半から1970年代の正規職員化闘争を通じて―
渋谷 光美 p.165
PDF<446KB>
韓国における障害者運動の原点
―韓国小児麻痺協会の活動と「障害問題研究会ウリント」の結成と勢力拡大までに―
鄭 喜慶 p.177
PDF<402KB>
作業療法の現代史3・1981~1991
―「作業療法の核を問う」までの道筋とその着地点―
田島 明子 p.187
PDF<399KB>
カーシェアリングの利用実態について
―京都市における事例をもとに―
仲尾 謙二 p.199
PDF<562KB>
地域医療における住民組織の役割の歴史的検討
―白峰診療所および堀川病院の事例を中心に―
西沢 いづみ p.211
PDF<439KB>
医療的ケアが必要な難病単身者の在宅生活構築
―介護職への医療的ケア容認施策に向けた視点―
西田 美紀 p.223
Liberalism and Confucianism: Rights and Virtues
NIU Geping p.235
PDF<425KB>
家族の支援がない重度障害者の在宅移行支援体制の検討
―医療的ケアを要する単身のALS患者を対象として―
長谷川 唯 p.249
PDF<356KB>
「チョッパリ」とオクスニ
―小林勝の文学における植民者と「もう一つの」朝鮮―
原 佑介 p.261
PDF<508KB>
1960年代から1980年代までのテロリズムの特徴
―テロリズムの手段と政府によるテロ対策を中心に―
樋口 也寸志 p.273
PDF<367KB>
サンフランシスコ市における水道事業公営化への史的展開
森下 直紀 p.285
PDF<410KB>
学生支援者による障害学生支援の構図
―日本福祉大学における情報保障を手がかりとして―
安田 真之 p.299
PDF<339KB>
独居ALS患者の病状進行過程における住生活実態と諸課題
山本 晋輔 p.311
PDF<966KB>
北村鈴菜と三越百貨店大阪支店美術部の初期の活動
山本 真紗子 p.323
PDF<547KB>
研究ノート
京都における風致概念の変容過程に関する言説研究
岩田 京子 p.335
PDF<621KB>
概念と実践からみる近代日本の美育
小出 治都子 p.345
PDF<390KB>
視覚障害者の読書環境の歴史―1985年以降の電子書籍に注目して―
櫻井 悟史・植村 要
p.355
PDF<361KB>
代理懐胎で生まれた子どもの福祉―出自を知る権利の保障―
貞岡 美伸 p.365
PDF<384KB>
当事者組織による訪問介護事業所設立時における障害者自立支援法の制度的課題
―NPO法人スリーピースの事例より―
白杉 眞 p.375
PDF<347KB>
「ライトノベル」「少女小説」ジャンルの再検討
―両性一元的文学史観点からの再整理―
髙木 聡司 p.385
PDF<385KB>
書評
群れとカテゴリ――河合香吏編『集団――人類社会の進化』書評―
京都大学学術出版会、2009年、364p.
石田 智恵 p.393
PDF<203KB>
思想を翻訳する方法と意図
―山田博雄著『中江兆民 翻訳の思想』―
慶応義塾大学出版会、2009年、iv+264p.
岡田 清鷹 p.397
PDF<210KB>
戦慄の経験の民族誌
―ピエール・クラストル著『グアヤキ年代記――遊動狩人アチェの世界』書評―
毬藻 充(訳)、現代企画室、2007年、413+28p.
=Chronique des Indiens Guayaki: ce que savent les Aches, chasseurs nomades du Paraguay. Plon, 1972
近藤 宏 p.401
PDF<219KB>
不連続性の視点
―クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理III 食卓作法の起源』書評―
渡辺公三・榎本譲・福田素子・小林真紀子(共訳)、みすず書房、2007年、604+51p.
=L’origine des manières de table. Plon, 1968
近藤 宏 p.405
PDF<215KB>
人間の思考と動物
―クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理IV 裸の人1,2』書評―
吉田禎吾・木村秀雄・中島ひかる・廣瀬浩司・瀧浪幸次郎(共訳)、(1)
吉田禎吾・渡辺公三・福田素子・鈴木裕之・真島一郎(共訳)、(2)
みすず書房、2008年;2010年、896+86p. =L’homme nu. Plon, 1971
近藤 宏 p.409
PDF<352KB>
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.6 2010年
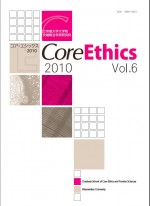
◇目次 PDF<308KB>
論文
1970 年代日本における精神医療改革運動と反精神医学
阿部 あかね p.1
PDF<411KB>
生体肝移植ドナーの負担と責任をめぐって
―親族・家族間におけるドナー決定プロセスのインタヴュー分析から―
一宮 茂子 p.13
PDF<388KB>
長期療養病棟の課題
―筋ジストロフィー病棟について―
伊藤 佳世子 p.25
PDF<426KB>
書籍のテキストデータ化にかかるコストについての実証的研究
―視覚障害者の読書環境の改善に向けて―
植村 要・山口 真紀・櫻井 悟史・鹿島 萌子 p.37
PDF<387KB>
歌川国芳《通俗水滸伝豪傑百八人之一個》におけるほりものの分析と考察
大貫 菜穂 p.51
PDF<1189KB>
上方浮世絵にみるほりものの発露―梅国と北州の「夏祭浪花鑑」より―
大貫 菜穂 p.65
PDF<735KB>
『わたしはティチューバ』における黒人奴隷制への抵抗
大野 藍梨 p.75
PDF<444KB>
『民約訳解』再考―中江兆民と読者世界―
岡田 清鷹 p.87
PDF<474KB>
初期ビデオゲームにおけるアニメーション技術の活用とその系譜
―『EVR レース』を中心に―
尾鼻 崇 p.99
「寝たきり予防」から「介護予防」へ
―そこで語られてきたこと―
各務 勝博 p.109
PDF<355KB>
下村治経済理論の一考察―経済成長と金融調整のあり方をめぐって―
影浦 順子 p.121
PDF<417KB>
ウィル・キムリッカのネイション概念
―キムリッカ多文化主義論における、こどもという問いの不在―
片山 知哉 p.133
PDF<399KB>
滋賀県難病連絡協議会の結成
葛城 貞三 p.145
PDF<411KB>
なぜ〈給付〉ではなく〈貸付〉をするのか?
―Muhammad Yunus の〈貸付〉論と「市場社会」観の検討―
角崎 洋平 p.157
PDF<398KB>
建国初期イスラエルにおけるデイル・ヤーシーン事件の語り
―殺戮行為の糾弾と正当化―
金城 美幸 p.169
PDF<383KB>
各種娯楽における満足感およびテレビゲームに対するイメージ・感情の要因分析
小孫 康平 p.181
台湾鉄道における「民営化改革」をめぐる歴史とその政治
―戦後から1989 年「民営化改革」まで―
蔡 正倫 p.197
PDF<494KB>
代理懐胎における子どもの福祉―依頼者の親としての適格性―
貞岡 美伸 p.209
PDF<385KB>
重度障害者等包括支援に関する考察
―個別と包括の制度間比較―
佐藤 浩子 p.219
PDF<310KB>
『地名アイヌ語小辞典』から「厚い翻訳」を考察する
佐藤=ロスベアグ・ナナ p.229
在宅介護福祉労働としての家庭奉仕員制度創設と、その担い手政策に関する考察
渋谷 光美 p.241
PDF<425KB>
障害者雇用における合理的配慮の導入視点
―障害のあるアメリカ人法(ADA)の現状からの考察―
杉原 努 p.253
PDF<381KB>
認知症高齢者の作業療法における言説・研究の変容・編制過程
―1980・1990 年代のリハビリテーション雑誌の検討―
田島 明子 p.265
PDF<384KB>
精神科特例をめぐる歴史的背景と問題点
―精神科特例の成立および改正の議論から―
仲 アサヨ p.277
感染地域の社会経済的現状とWHO、医療中心型援助の限界
―ブルーリ潰瘍の事例―
新山 智基 p.287
PDF<410KB>
一九五〇年代における文化運動のなかの民俗芸能
―原太郎と「わらび座」の活動をめぐって―
西嶋 一泰 p.299
PDF<435KB>
重度進行疾患の独居者が直面するケアの行き違い/食い違いの考察
―ALS 療養者の一事例を通して―
西田 美紀 p.311
近代国民国家モデルについての考察―方法論的アプローチから―(英文)
牛 革平 p.323
PDF<157KB>
行政主導による精神保健福祉に関する普及啓発活動―その批判的考察―
萩原 浩史 p.339
自立困難な進行性難病者の自立生活―独居ALS 患者の介助体制構築支援を通して―
長谷川 唯 p.349
PDF<366KB>
1910 年代の内務官僚と国民統合の構想―田澤義鋪の青年論を中心に―
番匠 健一 p.361
PDF<535KB>
高齢者に対する新たな医療制度における「現役並み所得」概念
―2006 年度の医療制度改革関連法による公費負担を中心に―
牧 昌子 p.375
トランキライザーの流行―市販向精神薬の規制の論拠と経過―
松枝 亜希子 p.385
PDF<1014KB>
「花街らしさ」の基盤としての土地所有―下京区第十五区婦女職工引立会社の成立から― 松田 有紀子 p.401
PDF<638KB>
日本の精神医療保健関係者の脱病院観についての考察
―米国地域精神医療保健改革とそれについての議論をもとに―
三野 宏治 p.413
PDF<384KB>
難民になれない庇護希望者―米加間の「安全な第三国」協定の影響―
本岡 大和 p.425
PDF<364KB>
ダム・ディベート―サンフランシスコの水源開発にともなう景観価値と国立公園―
森下 直紀 p.437
PDF<451KB>
重度身体障害者の居住支援
―単身ALS 罹病者の転居事例を通して―
山本 晋輔 p.451
PDF<374KB>
阪急百貨店美術部と新たな美術愛好者層の開拓
山本 真紗子 p.461
PDF<504KB>
在日韓国・朝鮮人のアイデンティティと多文化共生の教育
―民族学級卒業生のナラティブ分析から―
梁 陽日 p.473
PDF<391KB>
ある精神障害者の語りと生活をめぐる一考察
―「支援」は何を意味する言葉か―
吉田 幸恵 p.485
PDF<410KB>
研究ノート
スリランカの農村・農園の妊婦の健康と潜在能力
磯邉 厚子 p.497 PDF<413KB>
膵島移植レシピエントの期待と現実
―1 型糖尿病患者のインタビュー調査より―
一宮 茂子 p.509
PDF<411KB>
風景整備政策の成立過程
―1920‐30 年代における京都の風致地区の歴史的位置―
岩田 京子 p.519
PDF<457KB>
日本土木建設業の近代化と「朝鮮人」労働者の移入
大村 陽一 p.529
PDF<469KB>
自立生活センターの組織に関する研究
―運動と事業のバランスを保つための方策―
白杉 眞 p.541
PDF<375KB>
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.5 2009年
論文
1990 年入管法改正を経た〈日系人〉カテゴリーの動態
――名づけと名乗りの交錯を通して――
石田 智恵 p.1
PDF
明治期の土木建設業と「朝鮮人」労働
――京釜鉄道建設と日本土木建設業の進出――
大村 陽一 p.11
PDF
マックス・スタイナーの映画音楽にみる「ミッキー・マウシング」の手法
尾鼻 崇 p.25
家庭用ビデオゲームにおける「音楽」の誕生
――ファミリーコンピュータと『ドンキーコング』を中心に――
尾鼻 崇 p.35
滋賀県難病連絡協議会の運動の展開
葛城 貞三 p.47
PDF
庶民金庫の貨幣貸付に対する「潜在能力」アプローチ
――グラミン銀行との比較における考察――
角崎 洋平 p.59
PDF
Gender and Body Construction in Edo Period Kabuki
GABROVSKA Galia Todorova p.71
PDF
京都における公設浴場の設置過程及び運営に関する考察
川端 美季 p.89
韓国少女マンガにおける日本少女マンガの受容
――初期少女マンガの視覚表現を中心に――
金 素媛 p.99
老兵文学における家族表象
――履彊と張大春の比較を中心に――倉本 知明 p.111
PDF
他者の歴史を人類学者が問うことについて
――口承研究に見る主体モデルの検討――
近藤 宏 p.123
PDF
台湾鉄道はいかに台湾経済に影響を与えてきたのか
――台湾鉄道の歴史的・経済的文脈の考察から――
蔡 正倫 p.133
PDF
ベーシックインカム(BI)論者はなぜBI にコミットするのか?
――手段的なBI 論と原理的なBI 論について――
齊藤 拓 p.149
PDF
人工内耳装用児におけるリテラシー・言語・学力
坂本 徳仁 p.161
PDF
斬首を伴う「死刑執行人」の配置に関する考察
――公事方御定書から旧刑法にいたるまで――
櫻井 悟史 p.171
PDF
重症新生児の治療をめぐる「話し合い」のガイドライン
櫻井 浩子 p.181
PDF
代理出産の自己決定に潜むジェンダーバイアス
貞岡 美伸 p.191
PDF
翻訳者としての知里真志保――アイヌ神謡と詩――
佐藤=ロスベアグ・ナナ p.201
障害者雇用率制度における「ダブルカウント方式」の考察
杉原 努 p.217
PDF
日本における受精卵診断の認可枠組み転換の背景
利光 恵子 p.229
PDF
オンラインセルフヘルプグループの可能性
中田 喜一 p.241
ブルーリ潰瘍問題をめぐる国際NGO の動向
――神戸国際大学ブルーリ潰瘍問題支援プロジェクトの果たしてきた役割を中心に――
新山 智基 p.251
PDF
京都におけるアニメーション制作
――J・O・スタジオ・トーキー漫画部の活動より――
萩原 由加里 p.261
PDF
テロリストの選択理論モデル
樋口 也寸志 p.273
PDF
老年者控除の廃止がもたらした影響
――2004 年度与党「税制改正大綱」を背景として――
牧 昌子 p.283
抗うつ剤の台頭
――1950 年代~ 70 年代の日本における精神医学言説――
松枝 亜希子 p.293
PDF
台湾時代における川合三良の文学作品
――ある在台内地人作家にとっての皇民化政策――
松尾 教史 p.305
PDF
日本におけるクラブハウス言説の潮流についての研究
三野 宏治 p.315
PDF
「男女平等」を拒否する「女解放」運動の歴史的意義
――「男女雇用平等法」に反対した京都のリブ運動の実践と主張から――
村上 潔 p.327
PDF
「コンサベーション」の理念
――アメリカ合衆国自然保護運動の発展と資源管理政策――
森下 直紀 p.339
PDF
〈自己物語論〉再考
――アーサー・フランクの議論を題材に――
山口 真紀 p.351
日本画家・尾竹竹坡の画業について
――抒情画家・蕗谷虹児を理解するために――
山中 夕起子 p.361
PDF
蕗谷虹児、さまざまな「抒情画」のかたち
――パリ時代、アニメーション映画『夢見童子』について――
山中 夕起子 p.371
PDF
差別の社会理論における課題
――A. メンミとI. ヤングの検討を通して――
山本 崇記 p.381
PDF
明治京都における官製「美術」概念の受容
――京都の博覧会と美術商・「美術館」をめぐって――
山本 真紗子 p.393
PDF
GID 正規医療の「QOL」/当事者の「QOL」
――MTF 当事者への聞き取りから――
吉野 靫 p.403
〈異なる身体〉の交感可能性
――コンテンポラリー・ダンスを手がかりに――
渡邉 あい子 p.415
PDF
研究ノート
〈日系人〉というカテゴリーへの入管法改正の作用
――1990 年以降の出稼ぎ日系人に関する研究動向――
石田 智恵 p.427
PDF
「見る」ことから「触る」こと
――ミュージアムにおける「触れさせる」展示の試み――
鹿島 萌子 p.435
『神話論理』の解読に関する一考察
近藤 宏 p.443
PDF
アメリカバークレー市における障害者自立生活
――1989 年の障害者自立生活者を事例として――
定藤 邦子 p.453
PDF
A Comparison of Tagore’s Nationalism and Sun Yat-sen’s The Three
Principles of the People from the Perspective of Nationalism
NIU Geping p.463
PDF
若者の労働運動
――首都圏青年ユニオンの事例研究――
橋口 昌治 p.477
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.4 2008年

論文
R・ローティの「リベラリズム」
――その論理構造の究明――
安部 彰 p.1
PDF
出版社から読者へ、書籍テキストデータの提供を困難にしている背景について
植村 要 p.13
PDF
社会的な救済としての「犯罪被害者」
――60・70年代の日本の被害者学と補償論の考察から――
大谷 通高 p.25
PDF
境する運動と変容する主体
――ジャテックの脱走兵支援運動・米軍解体運動を中心に――
大野 光明 p.37
PDF
ナセリズムにおける「アラブ民族主義」の再検討
――革命初期のイデオロギー変容と外交政策の展開を中心として――
小川 浩史 p.51
PDF
映画『男の敵』の音楽分析
尾鼻 崇 p.67
日本軍軍事施設から多文化的国民空間へ
――三重【ルビ:サンチョン】市における空軍一村を中心に――
倉本 知明 p.79
PDF
死刑存廃論における「死刑執行人」の位置についての一考察
――日本の公文書に見る死刑執行現場の生成と消滅――
櫻井 悟史 p.93
PDF
障害新生児の治療をめぐる「クラス分け」ガイドライン
――その変遷と課題――
櫻井 浩子 p.105
PDF
障害当事者運動における介助者の役割
――大阪青い芝の会の運動におけるグループ・ゴリラを事例として――
定藤 邦子 p.119
PDF
植民地都市をめぐる集合的記憶
――「たうんまっぷ大連」の形成プロセスを事例に――
佐藤 量 p.131
PDF
道徳化する映画とミュンスターバーグの映画美学
――The Photoplay:A Psychological Study (1916) の文化的美学的前提から――
篠木 涼 p.149
PDF
少女小説における共同性と大量消費
――榎木洋子『影の王国』という実践的批判より――
高木 聡司 p.161
PDF
作業療法の現代史・1965~1975
――医療職化と独自性のはざまで――
田島 明子 p.175
PDF
日本における受精卵診断をめぐる論争(1990年代)
――なにが争われたのか――
利光 恵子 p.193
PDF
ポスト社会主義モンゴル国における遊牧民と土地私有化政策
――地方社会の土地利用に関する方法論的考察――
冨田 敬大 p.213
PDF
ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について
中倉 智徳 p.227
PDF
An Exploration of the Concept of the Modern Nation State: The Case of China
NIU Geping p.237
PDF
なぜ外国籍の子の教育政策は進まないのか?
――X地域を事例として――
能勢 桂介 p.251
PDF
1930年代から40年代の日本アニメ製作
――手引書を中心に――
萩原 由加里 p.265
心神喪失者等医療観察法における強制的処遇とソーシャルワーク
樋澤 吉彦 p.305
PDF
トラブルを起こす/トラブルになる
―1990年「府中青年の家同性愛者差別事件」と1991年から1997年の「府中青年の家裁判」を事例として―
藤谷 祐太 p.319
PDF
「動機の語彙」論再考
――動機付与をめぐるミクロポリティクスの記述・分析を可能にするために――
藤原 信行 p.333
PDF
「パート」問題を捉える視座としての「主婦」問題・「労働」問題
――<主婦の立場から女解放を考える会>・<パート・未組織労働者連絡会>の試みから――
村上 潔 p.345
PDF
差別論の現代史
――社会運動との関係性から考える――
山本 崇記 p.359
PDF
美術商山中商会
――海外進出以前の活動をめぐって――
山本 真紗子 p.371
PDF
「多様な身体」が性同一性障害特例法に投げかけるもの
吉野 靫 p.383
PDF
研究ノート
少年法改正をめぐる犯罪被害者遺族の言明
――2000年の少年法改正をめぐる言説――
大谷 通高 p.395
PDF
公衆浴場の法的規制における欠格条項の変遷
川端 美季 p.407
PDF
パレスチナ/イスラエルの「1948年」論争
金城 美幸 p.417
PDF
神話に読み取られたものについて
――1950年代のレビィ=ストロースの神話研究の考察――
近藤 宏 p.427
PDF
音楽療法士の労働実態と生活に関する一考察
――いま音楽療法の臨床で起こっていること――
坂下 正幸 p.437
PDF
在日フィリピン人の関係についての人類学的考察
――「日本国籍」をもつ人の事例――
永田 貴聖 p.457
PDF
向精神薬への評価
――1960年代から80年代の国内外における肯定的評価と批判――
松枝 亜希子 p.465
PDF
「保全」概念の源流と資源管理行政の成立
――20世紀初頭におけるアメリカ合衆国環境思想に関する一考察――
森下 直紀 p.475
PDF
グローバル化に伴う民営化を考察する
――郵便事業の事例を中心に――
 p.485
p.485
PDF
国内植民地としての台湾と台湾二・二八事件
 p.497
p.497
PDF
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.3 2007年

*正誤表
論文
障害学生支援の構図
――立命館大学における視覚障害学生支援を手がかりとしての考察――
青木 慎太朗 p.1
PDF
スティグマ化された家族の多様性の「発見」
――英語圏の発達心理分野におけるLesbian-family比較研究の検討――
有田 啓子 p.13
PDF
International Relations After Unipolarity and Deconstruction
池田 浩章 p.27
PDF
聴覚障害児の言語獲得における多言語状況
上農 正剛 p.43
PDF
変容する身体の意味づけ
――スティーブンスジョンソン症候群急性期の経験を語る――
植村 要 p.59
PDF
エジプト1952年革命と『革命の哲学』
――「ナショナル・アイデンティティ」の構築――
小川 浩史 p.75
PDF
マックス・スタイナーの映画音楽における作曲技法
――『キングコング』(1933)の音楽にみられるライトモティーフの手法を中心に――
尾鼻 崇 p.89
血友病者から見た「神聖な義務」問題
北村 健太郎 p.105
PDF
イスラエルにおける歴史記述とパレスチナ難民問題
――ベニー・モリスの歴史記述を中心に――
金城 美幸 p.121
PDF
ワークフェア構想の起源と変容
――チャールズ・エヴァーズからリチャード・ニクソンへ――
小林 勇人 p.133
PDF
「望まない強制妊娠」をした性被害女性への支援活動と被害者女性の人権
――産む・産まないの二項対立を超えて――
小宅 理沙 p.143
PDF
音楽療法における専門性と資格化をめぐる言説
――音楽療法界において何が語られてきたのか――
坂下 正幸 p.165
PDF
大阪における障害者自立生活運動
――1970年代の大阪青い芝の会の運動を中心に―
定藤 邦子 p.183
PDF
知里真志保と詩人たち――(1)『ユーカラ鑑賞』の共著者小田邦雄―
佐藤=ロスベアグ・ナナ p.197
PDF(WEB非公開)
初期の映画理論とその受容についての一考察
――K・ランゲとH・ミュンスターバーグ――
篠木 涼 p.213
沖縄県の「ふれあい工場【ルビ:こうば】」における精神障害のある人の就業及び生活支援に関する考察
杉原 努 p.223
PDF
企業の社会貢献と大義
――ピンクリボン活動の事例にもとづいて――
高田 一樹 p.239
PDF
花街の真正性と差異化の語り
――北野上七軒と五番町をめぐって――
竹中 聖人 p.249
PDF
社会受容論考
――「元の身体に戻りたい」と思う要因についての検討をめぐる「社会受容」概念についての一考察――
田島 明子 p.261
PDF
大正期における中井宗太郎の思想展開
――土田麦僊の実践を通して――
田野 葉月 p.277
PDF
北村透谷「内部生命論」と明治浪漫主義
福田 知子 p.291
PDF
近親者の自殺、意味秩序の再構築、動機の語彙
藤原 信行 p.301
PDF
治療を中止させない権利についての一考察
――英国Leslie Burke裁判をめぐって――
的場 和子 p.315
PDF
経済学における衡平性の比較検討
村上 慎司 p.337
PDF
戦後「市民」思想の形成過程とその陥穽
――松田道雄と社会運動――
山本 崇記 p.349
PDF
差別/被差別関係の論争史
――現代(反)差別論を切り開く地点――
山本 崇記 p.363
PDF
精神医療論争
――電気ショックをめぐる攻防――
吉村 夕里 p.375
PDF
台湾新式郵便制度の設立をめぐる一考察
――基隆の事例を中心に――
 p.391
p.391
PDF
研究ノート
「障害受容」は一度したら不変か
――視覚障害男性のライフストーリーから考える――
田島 明子 p.409
PDF
テロリストに対する行動の経済学的アプローチ
――基本所得はテロを防ぐ政策として有効か?――
樋口 也寸志 p.421
PDF
延命治療の差し控え/中止に関するガイダンス:紹介
――英国General Medical Council編:延命治療の差し控えと中止:意思決定のよき実践のために――
的場和子・堀田義太郎・有吉玲子・末岡陽子 p.433
PDF
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.2 2006年

◇目次
論文
R・ローティ「人権」論の精査
――その批判的継承に向けて――
安部 彰 1
pdfファイル(71KB)
迫られる「親」の再定義
―法的認知を求めるアメリカのlesbian-motherが示唆するもの―
有田 啓子 17
pdfファイル(64KB)
マイノリティの都市戦略
―京都祇園の資望と構造―
大村 陽一 31
pdfファイル(71KB)
ムスリム同胞団の誕生とその歴史的展開 1906-1940
―イスラーム復興運動の暴力化のプロセスを中心として―
小川 浩史 45
pdfファイル(72KB)
「湯屋取締規則」及び「湯屋營業取締規則」に関する考察
川端 美季 59
pdfファイル(82KB)
血液利用の制度と技術
――戦後日本の血友病者と血液凝固因子製剤―
北村 健太郎 75
pdfファイル(63KB)
全国ヘモフィリア友の会の創立と公費負担獲得運動
北村 健太郎 89
pdfファイル(58KB)
初期ワークフェア構想の帰結
―就労要請の強化による福祉の縮小―
小林 勇人 103
pdfファイル(57KB)
ベーシックインカムとベーシックキャピタル
齊藤 拓 115
pdfファイル(67KB)
大阪・兵庫の障害者自立生活運動の原点
定藤 邦子 129
pdfファイル(52KB)
Cause Related Marketingによる2つの利益追求についての研究
―「乳がんで亡くなる患者を減らす」という大儀を企業の利益に結びつけるビジネスの事例にもとづいて―
高田 一樹 141
pdfファイル(66KB)
歴史的環境としての花街とまちづくり
―北野上七軒を例に―
竹中 聖人 153
pdfファイル(83KB)
若年者の雇用問題と「やりたいこと」言説
橋口 昌治 165
pdfファイル(61KB)
「オール・ロマンス」糾弾闘争の政治学
―戦後部落解放運動史再考にむけて―
山本 崇記 181
pdfファイル(61KB)
近代国家形成における郵便制度の官営独占について
 195
195
pdfファイル(57KB)
研究ノート
Lesbian-motherの子育ては健全か
―発達心理学分野の実証研究とそれをめぐる議論―
有田 啓子 209
pdfファイル(67KB)
ヌワラエリヤの女性たち
―スリランカ農園部の母子保健における一考察―
磯邉 敦子 225
刑事司法における二次被害
―二次被害の概観と整理―
大谷 通高 233
犯罪被害女性の妊娠に対する支援の実態と今後の課題
小宅 理沙 247
pdfファイル(49KB)
福祉国家改革の一方向性
―各国に見る資産ベース福祉への移行―
齊藤 拓 259
pdfファイル(53KB)
立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』 vol.1 2005年
 ◇目次
◇目次
創刊の辞 ……………………………………………………………渡辺 公三
pdfファイル(7KB)
論文
「錆びた炎」問題の論点とその今日的意義 …………………… 北村 健太郎 1
pdfファイル(55KB)
クルアーン研究における文化装置論的アプローチ
―プラチックとしての聖典― …………………………………… 小杉 麻李亜 15
文部省美術展覧会における美人画様式の変遷に関する考察
―第9回文展美人画室論争からみえるもの― ………………… 田中 圭子 29
在日フィリピン人女性による日常の「戦術」
―ある女性のライフストーリーを中心に― ……………………… 永田 貴聖 41
科学知識の伝達
―スーパースプレッダーの例― ………………………………… 横田 陽子 57
pdfファイル(107KB)
研究ノート
公共財の公共性
―道路の場合― ………………………………………………… 大谷 雅人 73
pdfファイル(37KB)
知里真志保のフィールドメモ
―1942年の夏― …………………………………… 佐藤=ロスベアグ・ナナ 83
社会的責任投資の動向とその課題 ……………………………高田 一樹 95
pdfファイル(45KB)
「自己決定/自律」および「自己決定権」についての基礎的考察
―支援/介入の観点から― …………………………………… 樋澤 吉彦 105
pdfファイル(53KB)
著書(共著、共編を含む)
2010.08.13 (細川周平と共編)『うつろ舟-ブラジル日本人作家 松井太郎小説選』松籟社
(解説文「外地日本語文学の新たな挑戦/松井太郎文学とその背景」pp. 308-314)
連載
2010.05.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑫時間の糸(『すばる』5月号、集英社)
2010.06.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑬音の転生(『すばる』6月号、同上)
2010.07.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑭老人の性(『すばる』7月号、同上)
2010.08.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑮思春期ごっこ(『すばる』8月号、同上)
2010.09.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑯オナニストたち(『すばる』9月号、同上)
2010.10.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑰時間かせぎ(『すばる』10月号、同上)
2010.11.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑱アウトドア派(『すばる』11月号、同上)
2010.12.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑲群れと死(『すばる』12月号、同上)
2011.01.01 ターミナルライフ/終末期の風景⑳恥の技法(『すばる』1月号、同上)
その他、活字になったもの
(2009.08.27-8)口頭発表採録「日本文学の新拠点としてのブラジル(O Brasil como uma nova base da Literatura Japonesa)」,Anais do XX Encontro Nacional de Professores Universit?rios de L?ngua, Literatura e Cultura Japonesa, “Para al?m do Jap?o: Brasil, Canad? e Fran?a, 37-62.
2010.07.15 口頭発表採録「元日本兵のディアスポラ」in『植民地文化研究』第9号、pp. 15-20.
2010.12.15 事典項目「擬人法表現」in『宮澤賢治イーハトヴ学事典』(天沢退二郎・金子務・鈴木貞美編、弘文堂)pp. 120-121.
2011.03 口頭発表採録 “Miyazawa Kenji and Global Justice”, in Artistic Vagabondage and New Utopian Projects, ed. by Shigemi INAGA, International Research Center for Japanese Studies, pp. 37-42.
2011.03.31 論文「日本語文学の越境的な読み方に向けて」in『立命館言語文化研究』22巻4号、国際言語文化研究所、p. 179-186.
翻訳
2010.11.20 イツホク・バシェヴィス「ギンプルのてんねん」in『〔池澤夏樹・個人編集〕世界文学全集Ⅲ-06:短編コレクション』(河出書房新社)、pp. 57-75【イディッシュ語から】
講演ほか、話したこと
2010.07.10 植民地文化学会シンポジウム「植民地主義と女性」(コメンテータ)於:東京都江東区東大島文化センター
2010.07.19 「日本語文学とボートピープル」(講演)於:大阪府立大学
2010.08.17 “Miyazawa Kenji and the Global Justice”, contribution to the workshop on “Intellectual Interaction in East Asia in 1920s and 30s”, 19th ICLA Conference(学会発表), Seoul, Chung-ang University(中央大学校)
2010.09.11 アメリカ文学会関西支部例会(ゲスト司会)「アメリカ時代のLafcadio Hearn-「ローカル・カラー」文学の観点から」(発表者:木田悟史)於:神戸女学院大学
2010.09.26 ラフカディオ・ハーン来日120年/生誕160年記念シンポジウム「ハーン来日120年-ハーンの魅力とその現代性」(パネリスト)、「『怪談』を読み直す」 於:熊本大学
2010.10.24 ロシア東欧学会・JSSEES 合同研究大会(討論者)「ポーランド・ロマン主義文学とマゾヒズム」(発表者:柴田恭子)於:天理大学
2011.11.07 日本比較文学会関西大会(研究発表司会)A室、於:京都産業大学
2010.11.26 国際言語文化研究所・秋季連続講座「グローバル・ヒストリーズ-国民国家から新しい共同体へ-〔第1シリーズ:トランスアトランティック‐トランスパシフィック〕第4回:カリブは周縁か?」(企画・司会・コメンテータ)於:立命館大学創思館カンファレンスルーム
2010.11.28 アートリサーチセンター連続講演会4〔若手研究者企画〕「文学・文化に見る韓国併合と「朝鮮」への眼差し-せめぎ合うイメージ、植民地帝国言説の両義性」(ディスカッサント)於:立命館大学国際平和ミュージアム会議室
2010.12.18 「リービ英雄を囲む座談会」(対話者)於:名古屋市大
2011.01.05 「インドネシア・韓国・日本共同セミナー」(司会)於:国立インドネシア大学文学部
2011.01.09 「宮沢賢治と擬人法」(研究発表)於:国際日本文化研究センター
2011.02.17 「作家・佐川光晴氏を囲んで」(司会)於:創思館401・402
主宰研究会活動
2010.04.04 第6回JAS(ユダヤ・ドイツ・スラヴ)研究会、於:京都大学
2011.03.13 第7回JAS(ユダヤ・ドイツ・スラヴ)研究会、於:京都大学
院生プロジェクトへの「責任教員」としての参加
研究科内公募研究会(研究代表者:倉本知明)「アジアン・ディアスポラ研究会」
2010.(04.23, 05.28) 06.25, 07.30, 10.08, 11.05, 12.17; 2011.03.10
生存学研究センター院生プロジェクト(研究代表者:雨宮幸明)「生存学と文学研究会」
2010.(05.07, 05.21, 06.04), 06.11, 07.02, 07.16, 09.17, 10.15; 2011.01.28, 02.17
学会活動ほか
日本比較文学会関西支部幹事・庶務委員、ICLA(国際比較文学会)会員
日本台湾学会会員、植民地文化学会会員、宮沢賢治学会会員
海外出張
2010.11.16-22 アメリカ合衆国・ニューヨーク市(大阪大学・圀府寺科研、名古屋市大・土屋科研)、YIVO研究所および市立図書館にて資料調査・収集
2011.01.04-07 インドネシア・ジャカルタ市(プール学院大・木村科研、名古屋市大・土屋科研)ワークショップへの参加


