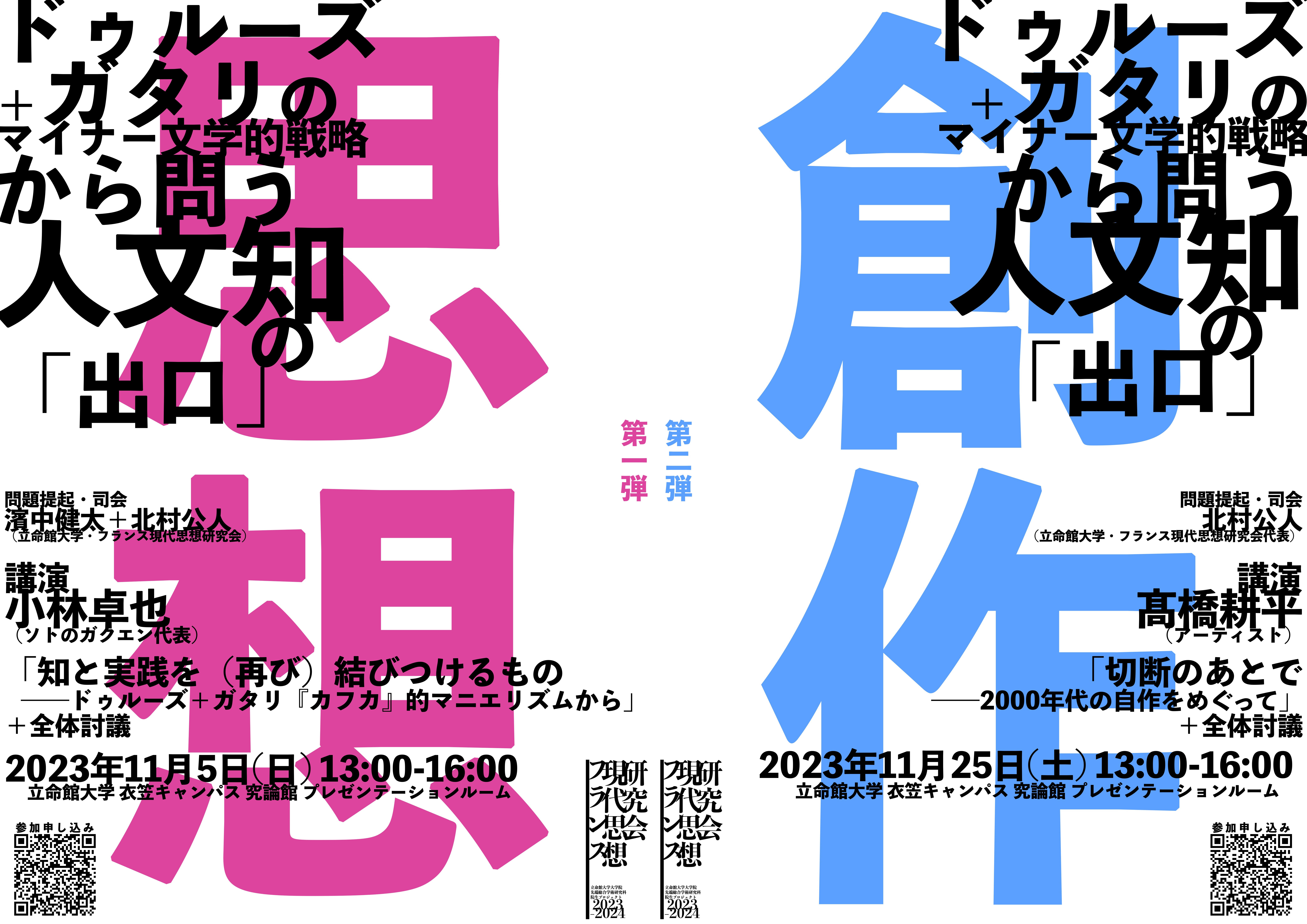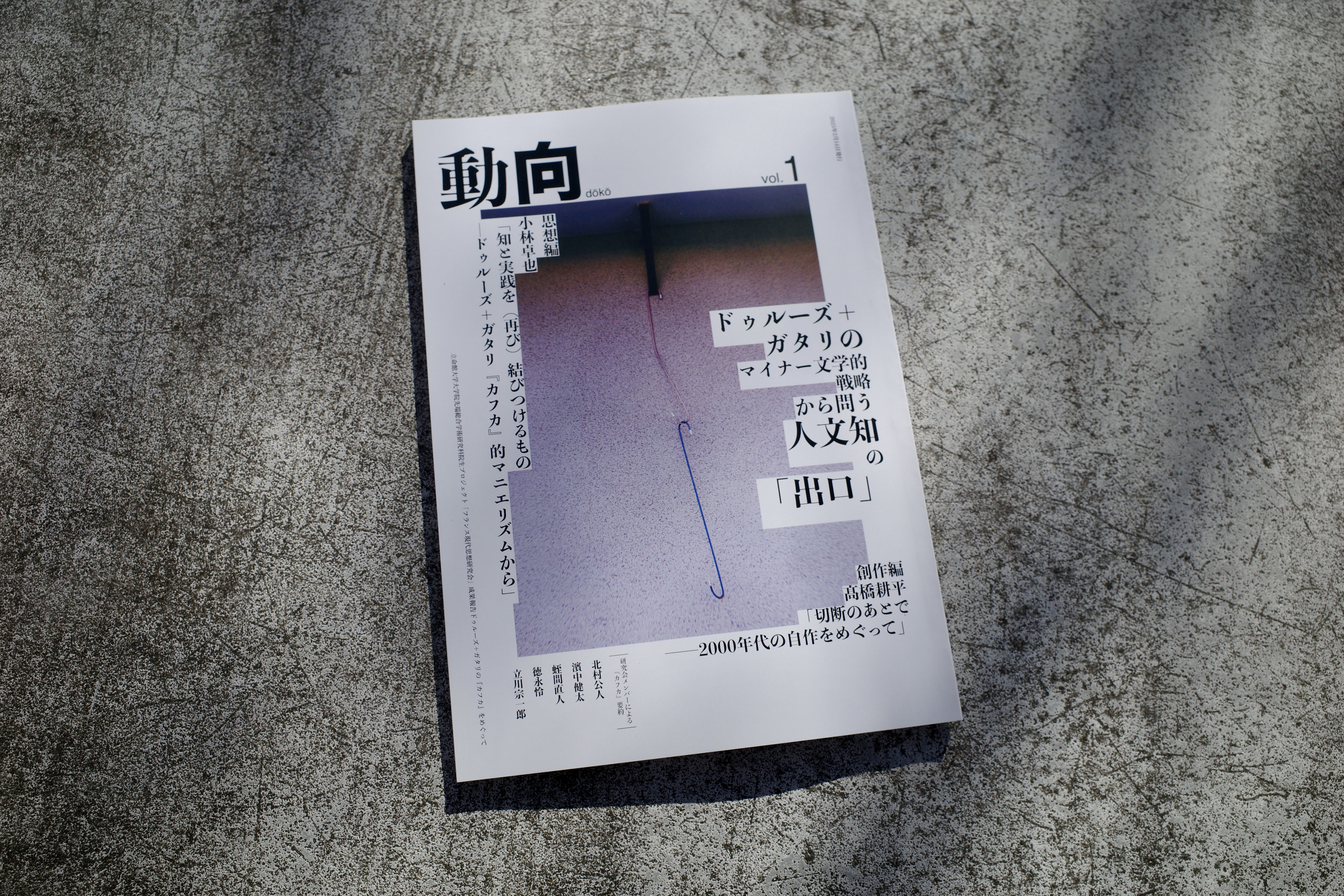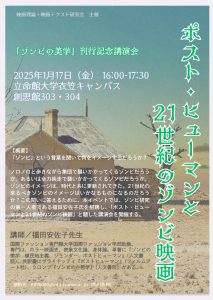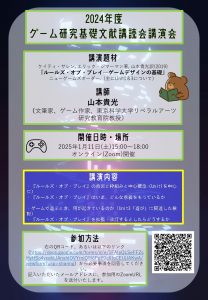<公開研究会テーマ>
ドゥルーズ+ガタリのマイナー文学的戦略から問う人文知の「出口」
<開催日時・会場>
【第一弾:思想編】
2023年11月5日(日)13:00~16:00(開場:12:30)
会場:立命館大学 衣笠キャンパス 究論館 プレゼンテーションルーム
ゲスト講師:小林卓也氏(ソトのガクエン代表)
講演「知と実践を(再び)結びつけるもの ——ドゥルーズ+ガタリ『カフカ』的マニエリズムから」
【第二弾:創作編】
2023年11月25日(土)13:00~16:00(開場:12:30)
会場:立命館大学 衣笠キャンパス 究論館 プレゼンテーションルーム
ゲスト講師:髙橋耕平氏(アーティスト)
講演「切断のあとで ——2000年代の自作をめぐって」
<公開研究会のコンセプト>
【第一弾:思想編】
冷戦が終焉した以降の世界では、人文知は実践的な価値を見失い、現代ではもはや役に立たない単なる「知識」に落ちぶれてしまったと言っても過言ではないでしょう。そのような現代的な状況の中で、それでも人文系を志してしまった者は、このような時代の変化に応じてサバイバルする方法を模索しなければなりません。
つまり、私たち大学院生は、「博士論文を書く」という目標をクリアするだけにとどまらず、「その研究内容を社会にどのように還元するか」を考えることが求められているわけです。
そのような時代状況の要請に応えるのはもちろんのことですが、さらに私たちが所属しているのは一般的な大学院ではなく、「先端総合学術研究科」です。したがって、一般的な大学で行われているような、研究テーマとなる分野の専門的かつ最新=「先端」の情報に精通するだけでなく、情報を領域横断的=「総合」的に判断する能力を鍛え、さらにそこから新たなフロンティア=「出口」(D+G『カフカ』でキーワードとなる語です)を開拓し、社会的な実践を思考することが、ここ、「先端」「総合」学術研究科では求められているわけです。
では、そのような「出口」を見出すにはどうしたら良いのか。
今回の公開研究会第一弾では、ドゥルーズ研究者として現在は京都産業大学で教鞭を執りつつも、その「ソト」で、私塾「ソトのガクエン」を運営している小林卓也さんをお呼びし、自身の「出口」である私塾の活動と、研究の関係性についてお話ししていただきます。その上で全体討議として、これまでに研究会で行った『カフカ』の議論をもとに、「自身の研究成果を社会的に役立つ形でどのように活用していくのか」という問題を、さらに深掘りします。
【第二弾:創作編】
ドゥルーズとガタリは『カフカ』において、カフカの創作について議論しており、特に、(例えばラカンにおける「ファルス」のような)特権的な意味作用から逃走すること、つまりは、(芸術)作品に対して一つの固定的な解釈を生み出そうとするあらゆる試みを妨害することがひとつのテーマになっています。
ドゥルーズとガタリによれば、カフカ作品というのは、例えば「カフカ=不条理文学」といったレッテルを貼り、一義的に解釈することを求めているのではないと言います。そうではなく、カフカ作品が私たちに提案しているのは、むしろ「解釈」という凝り固まった意味作用の結びつきをほどき、新たな「地図」を見つけ出す実験をしている(=「マイナー文学」と呼ばれます)と言うのです。
このドゥルーズとガタリのカフカ読解から、本研究会で議論になったのは、カフカのような「一義的な解釈や意味作用からの逃走」という実践は、カフカ以外であればどのようなものが当たるのか? また、この戦略というのは実際にはどのように応用可能か?ということです。ここでは特に、時間芸術である映像作品に着目し、議論しました。
そこで、今回の公開研究会第二弾では、京都を拠点に活動するアーティストの高橋耕平さん(映像を反復・複製することから発生するズレをテーマにした作品で知られる)をお呼びし、高橋さんのご自身の作品や、創作活動のプロセス等についてレクチャーをしていただきます。その上で、これまでの研究会で行ってきた『カフカ』の議論をまとめて発表し、カフカ以外の「マイナー文学的戦略」として、現代ではどのような「創作」が可能なのか、実際の芸術実践の側面から探ります。
〇参加申込
イベント当日までに下記フォームから参加の申し込みをお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnFb2lQ05x98syHyLMMB6_6Da-GkAVkbbSAVz1C_MPdZGA4Q/viewform
〇主催
立命館大学大学院 先端総合学術研究科 「フランス現代思想研究会」
問い合わせ:北村公人
gr0583pr@ed.ritsumei.ac.jp