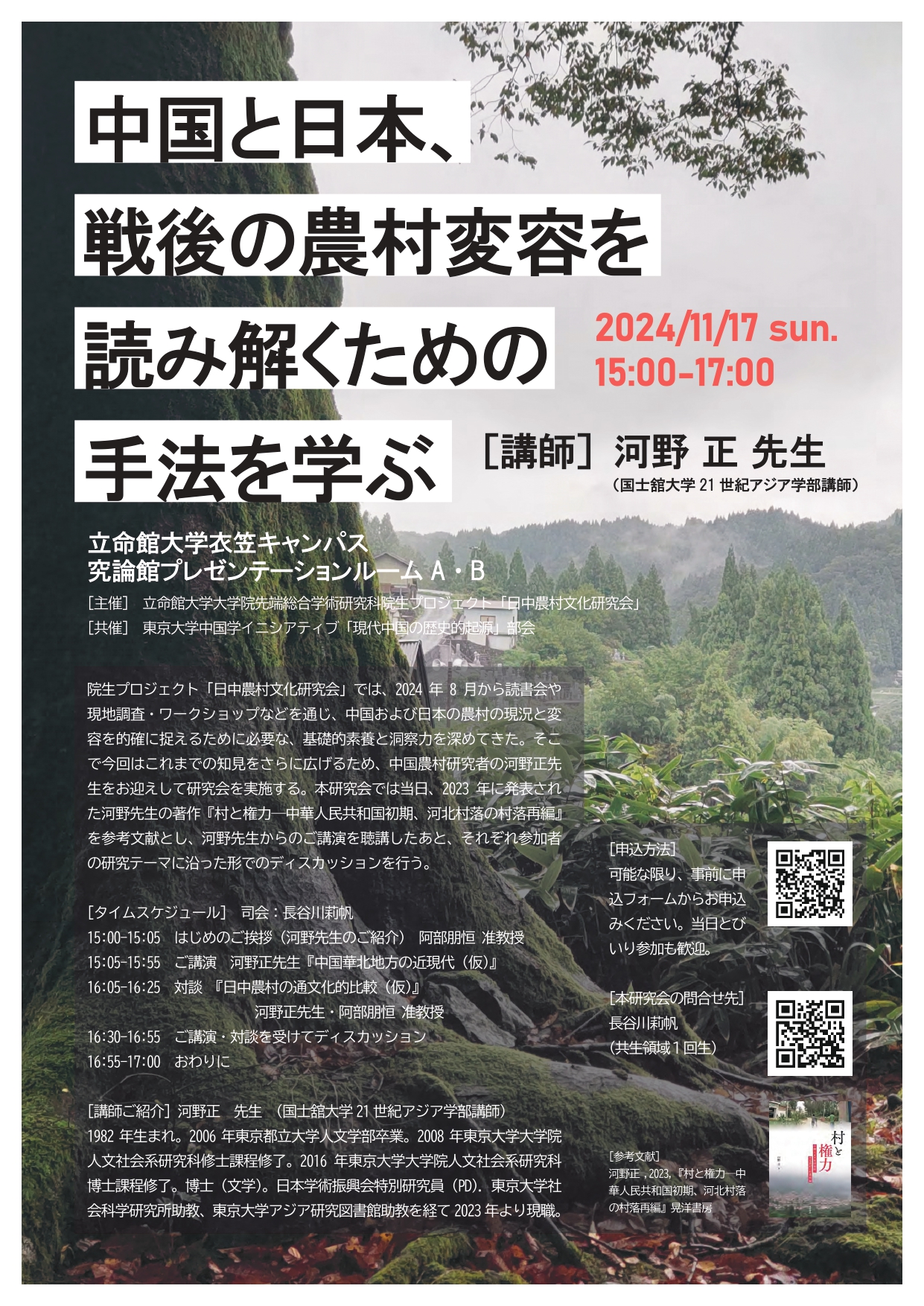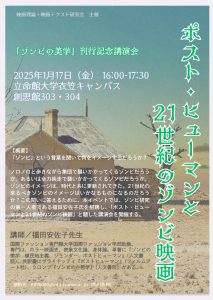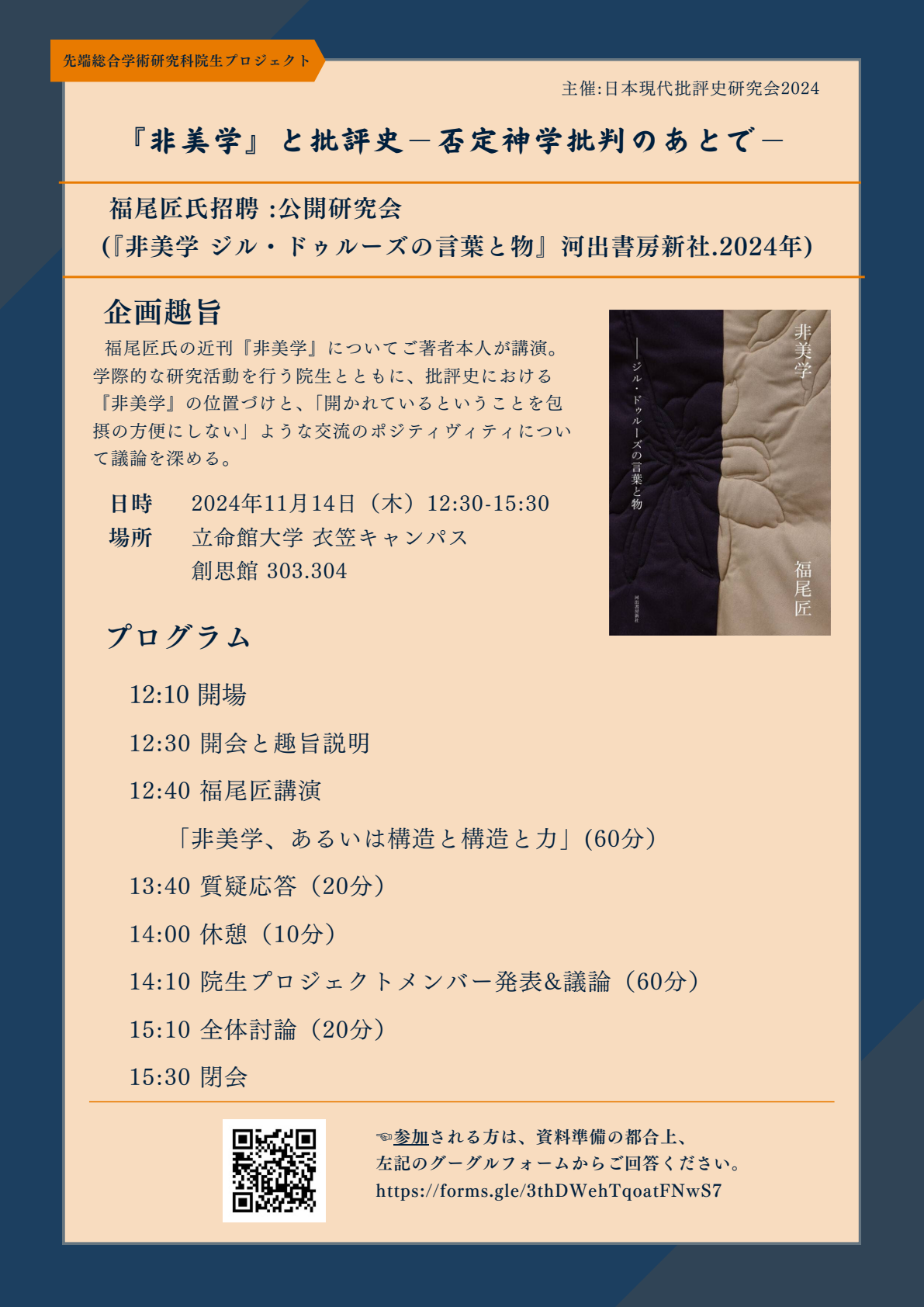2023年度 博士論文/博士予備論文構想発表会
先端研では、博士予備論文(修士論文に相当)・博士論文の構想発表会を行なっています。
構想発表会は、プロジェクト型教育・学際的研究を推進する先端研ならではの、多様な関心をもつ院生・教員・研究者らが集う貴重な機会です。ぜひこの場に参加して、先端研の魅力を体感してみてください。
2023年度 秋学期 博士論文/博士予備論文構想発表会
論題・スケジュール
開催概要
対面+Zoomのハイブリット形式。実施者は全員対面実施です。
日時:2024年2月6日(火)~2月7日(水)
会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館1階カンファレンスルーム
2024年2月6日(火)
- 14:00~14:35 <予備> (公共) 日本「ものづくり大国」イメージの起源と流布過程
- 14:35~15:10 <予備> (共生) 食から見る野生性とドメスティケーション―中国広州市における「了能菜」の例を中心に(仮)
- 15:20~15:55 <予備> (公共) 外国人研修・技能実習制度とその秩序
- 15:55~16:30 <予備> (表象) 生成としての遊び」を学習活動に応用する基礎的検討 ――無気力学習者向けの自主型授業設計の可能性
- 16:40~17:30 <博士> (共生) 高次脳機能障害のある人が選択する自己開示ーー受傷から就労までの戦略と葛藤
2024年2月7日(水)
- 10:00~10:50 <博士> (共生) 障害とセクシュアリティの交差――台湾における障害のある性的少数者の経験から
- 11:00~11:50 <博士> (表象) 20 世紀における中国年画の変容 ―民衆美術とプロパガンダ美術のはざま─
- 13:00~13:50 <博士> (共生) 平等主義的暴力の存在論:トゥワ・ピグミーのマルチモーダル民族誌
- 14:00~14:50 <博士> (表象) 日本における映画からテレビへのメディア・コンテンツの変遷-東映を中心に-
- 15:00~15:50 <博士> (公共) 「脳性麻痺」に行なわれた手術――1940年代~1970年代に着目して――(仮)
- 16:00~16:50 <博士> (表象) 1930年代日本の「音画」思想
- 17:00~17:50 <博士> (生命) 日本の自閉症施設とその周辺の歴史――戦前からの自閉症処遇前史と1960年代以降の専門施設の出現過程、そして施設設立とその支援にかかる制度化をめぐる動き――
2023年度 秋学期 博士論文/博士予備論文構想発表会
論題・スケジュール
開催概要
対面+Zoomのハイブリット形式。実施者は全員対面実施です。
2023年10月24日(火)
- 会場:衣笠キャンパス平井嘉一郎記念図書館カンファレンスルーム
- 13:30~14:20 <博士>(公共)日本の自閉症施設とその周辺の歴史――戦前からの自閉症処遇前史と1960年代以降の専門施設の出現過程、そして施設設立とその支援にかかる制度化をめぐる動き――
- 14:30~15:20 <博士>(表象)ダンス作品の存在論――虚実の二重性としてのパフォーマンスと作品――
2023年10月31日(火)
- 会場:衣笠キャンパス 創思館407、408教室
- 13:00~13:50 <博士>(公共)障がい者制度改革の研究――公共政策形成における当事者参画の意義と課題――
2023年度 春学期 博士論文/博士予備論文構想発表会
論題・スケジュール
開催概要
日時:2023年7月22日(土)~7月24日(月)
会場:立命館大学衣笠キャンパス創思館1階カンファレンスルーム
2023年7月22日(土)
- 10:00~10:35 <予備>(表象)『League of Legends』のランク戦における「強制敗北」言説の考察
- 10:40~11:15 <修士>(共生)中国における仏教系高齢者福祉施設による心のケアに関する考察 (仮)
- 11:25~12:00 <修士>(公共)クリエイティブ労働による職業生活の形成と継続──プロバンドマンを事例に
- 12:05~12:40 <予備>(表象)デジタルゲームにおける批判的で逸脱的な遊び〜「あつまれどうぶつの森」のアバターを中心に
- 14:10~14:45 <予備>(公共)盲ろう者たちの運動史 ――「複雑な困難」をめぐるもうひとつの障害者運動
- 14:50~15:25 <予備>(表象)データベースでは満足しないプレイヤー:ファンの考察から見る新しい消費
- 15:35~16:10 <修士>(表象)中西夏之、1960年代の制作と思考─物質と概念の結び目としての中西夏之論─
- 16:20~17:10 <博士>(公共)沖縄的共同体論とジェンダー―シングルマザーの生活史から
2023年7月23日(日)
- 10:00~10:35 <予備>(共生)繋がりを切断する実践についての考察― 楽器修理における 「即興的な修理技法」 を対象として―
- 10:40~11:15 <予備>(表象)武満徹における〈夢〉と〈数〉の詩学―1980年代の言葉と管弦楽曲を中心に
- 11:25~12:00 <予備>(表象)プレイヤーに与えられる手がかりの多様さ 〜ビデオゲーム攻略の類型論〜
- 12:05~12:40 <予備>(公共)現代中国における「自発的」長時間労働をめぐる社会学的研究
- 14:10~14:45 <修士>(公共))障害者施設コンフリクトを解消できなかった要因と背景にあるもの――京都府長岡京市の事例から
- 14:50~15:40 <博士> (共生)都市インナーエリアで紡がれる零細自営業のサブシステンスに関する社会学的研究――京都市出町における商実践を事例として
2023年7月24日(月)
- 10:40~11:15 <予備>(共生)現代中国における婚姻の転換 ――上海人民公園の「相親角」からの民族誌的研究
- 11:25~12:00 <予備>(表象)ジャック・ラカンにおける精神分析的主体の再検討─「喜劇的主体モデル」の構築に向けて─
- 12:05~12:40 <予備>(生命)現代中国における喫煙環境の変遷-法律と政策から見る現状-
- 14:10~14:45 <修士>(共生)「一人子」時代に生まれた若者たちの留学オデッセイ 中国人留学生サークル「M 会」のライフストーリーから
- 14:50~15:25 <修士>(公共)中国の健康診断制度より軽度肢体障害者の自己認識に与える影響
- 15:35~16:10 <修士>(共生)在日中国人の「顔が見える団購」を通した新たな「つながり」創出に関する人類学的研究
- 16:20~17:10 <博士>(公共)障害者制度改革の研究―公共政策形成における当事者参画の課題―
- 17:20~18:10 <博士>(表象)明治時代の日本音楽界における「エキスプレッション」の変遷――第一高等学校および東京音楽学校出身者の「音楽批評」をもとに
注意事項
発表者の方へ
- 時間配分
<博士論文構想発表会> 発表時間30分、質疑応答20分(合計50分)
<博士予備論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分)
<修士論文構想発表会> 発表時間15分、質疑応答20分(合計35分) - 発表は、論文のテーゼ・論旨に絞って、簡潔かつ明確に述べること。
- 発表時のレジュメ(A3片面印刷1枚)を、必ず予め50部用意して持参すること。
博士論文の構想発表でもA3判両面1枚までに必ずおさめてください。
また、レジュメのデジタルデータ(.docx あるいはPDF)をメールに添付して提出してください。
提出期限:7/20(木)17:00
送り先:doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp([at]を半角@に変更)
件名:「先端研 構想発表会資料(氏名)」としてください。
特に決まった書式はありません。 - レジュメには以下の事項を簡潔に記載すること。
・論文の主旨
・論文の章立て
・研究史上の意義
・主要参考文献
・必要なら図表 - 発表用原稿またはメモはレジュメとは別に各人において用意すること。
- 発表者で欠席する場合は、必ず件名に「先端研」と入れて下記まで連絡してください。doku-ken[at]st.ritsumei.ac.jp ([at]を半角@に変更)
- 発表用に使用する機器類については事前に事務室に申し出ること。
先端研院生の方へ
- やむを得ぬ事情のあるときを除き、先端総合学術研究科の大学院生は全員参加を原則としています。特に新入生の方は、次年度の発表に向けて (授業との重複を除き)ご参加ください。
過去の博士論文・博士予備論文構想発表会
2022年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2021年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2020年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2019年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2018年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2017年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2016年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2015年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2014年度 博士論文・博士予備論文構想発表会
2013年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会
2013年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会
2012年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会
2012年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会
2011年度後期 博士論文・博士予備論文構想発表会
2011年度前期 博士論文・博士予備論文構想発表会