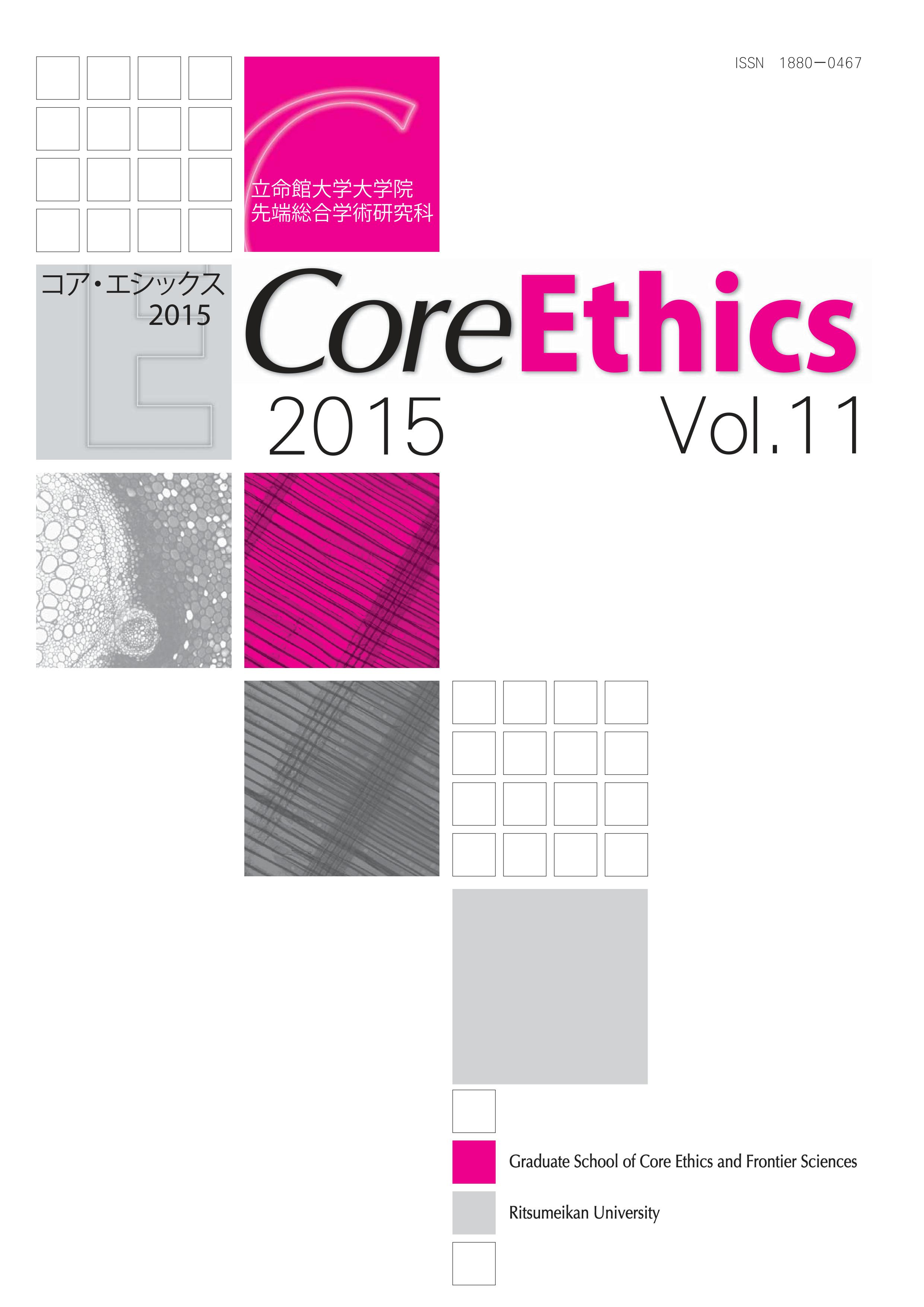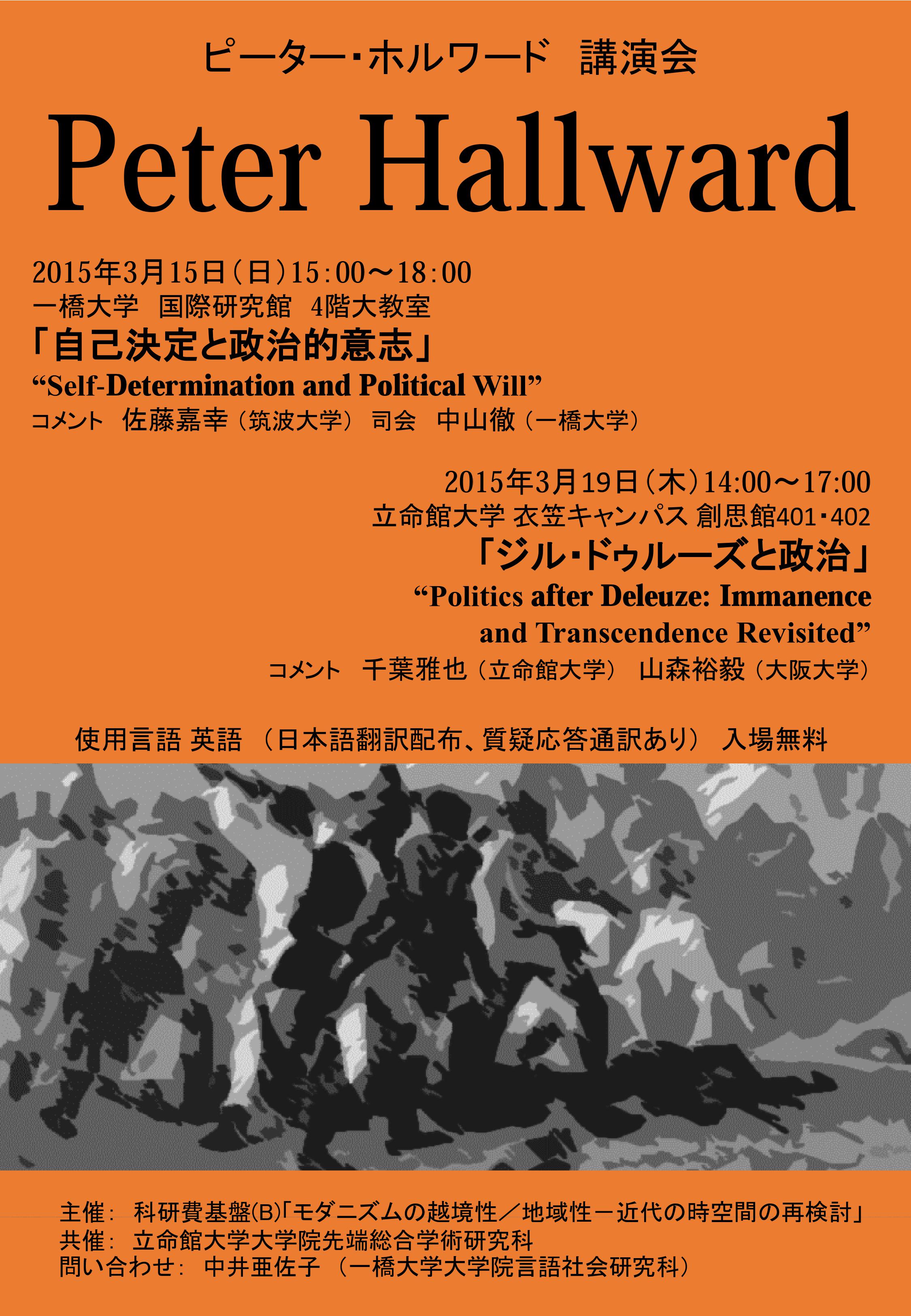院生代表者
- 古田 賢
教員責任者
- 千葉 雅也
企画目的・実施計画
本研究会は、服飾(ファッション・民族衣装・コスチュームなど)を表象文化の観点から研究することを目的としている。メンバーの研究領域は、服飾研究のみならず、ゲーム、スポーツなど多岐にわたっており、服飾について多角的な検討が可能となる。また、服飾文化を研究テーマにしているメンバーも服飾以外の知見を得ることができ、各自の研究にも成果がフィードバックされることが期待できる。これらの研究会活動によって表象文化研究に対して服飾という視点から貢献ができる。加えて、メンバーの半分以上が1・2回生であり、様々な学問分野に授業以外で触れることができる利点もある。
研究会活動は、メンバーの研究関心に沿った研究発表を行い、ディスカッションを通じてメンバーの知見を高め、自身の研究分野とファッションを結びつけたテーマを設定する。最終的には、年度末に研究報告発表会を開催し、各自が研究成果を公表することを目標とした。また、今年度は外部からの講師を招いた講演会も企画する。
活動内容
今年度、本研究会では初めて講師を招いた講演会を開催した。これまで、本研究会では、思想に関わる議論はごく僅かであったため、美学者である谷川渥氏を招いた。この講演会は、美学を含む思想と服飾文化の関係を考えていくことが、本研究会に多大な意義があると考え企画した。
昨年度は、ディスカッションが中心だったため、今年度は、研究会メンバーによる発表を中心に行った。発表内容は服飾史をはじめ、マスメディア、ゲームなど各自の研究に関係するものであった。2016年2月には、昨年度同様に、研究会活動の成果を発表する研究発表会を行った。
- 第1回研究会
- 第2回研究会
- 第3回研究会
- 講演会「〈作品〉のトポロジー」
- 第5回研究会
発表者:後山 剛毅
日時:7月13日(月)17:00~19:00
場所:究論館プレゼンテーションルームB
発表者:ショウ ガン
日時:2015年8月27日(木)17:00~19:00
場所:究論館プレゼンテーションルームB
発表者:古田 賢・シン ジュション
日時:2015年10月29日(木)17:00~19:00
場所:究論館プレゼンテーションルームA
日時:11月24日(火) 18:00~20:00
場所:存心館4階904教室
講演タイトル:〈作品〉のトポロジー
講演者:谷川渥
講演要旨:
作品とは何か。作者、作品、鑑賞者(享受者)の三項関係が最も常識的だが、この三者の関係をとらえ直すことで、作品のトポロジーを構成してみたい。実存の美学の試みである。
事前申し込み不要、参加費無料
発表者:1 古田 賢 2 根岸 貴哉・枝木 妙子 3 後山 剛毅
日時:2月8日(月)13:00~15:00(1組の発表時間は40分)
場所:創思館412教室
成果及び今後の課題
今年度は各メンバーによる発表を中心に行ったため、各自の発表スキルの向上につながった。また、今年度は初めて外部から講師を招いた講演会を行ったことで、研究会活動を外部にも発信することができた。これを機に、研究会の参加者を学内だけでなく、学外からも多く招き、幅広い議論を行いたい。そのために、今後は外部の参加者を招くイベントを積極的に企画したいと考えている。これらの研究会活動の延長として、学会発表や論文投稿につなげていきたい。
構成メンバー
古田 賢 表象領域 4回生 2014年度入学
枝木 妙子 表象領域 3回生 2013年度入学
根岸 貴哉 表象領域 2回生 2014年度入学
シン ジュヒョン 共生領域 2回生 2014年度入学
ショウ ガン 表象領域 2回生 2014年度入学
後山 剛毅 表象領域 1回生 2015年度入学