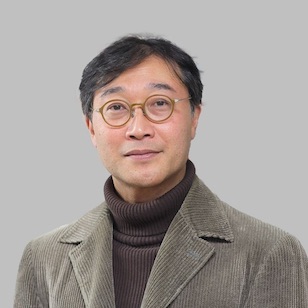立命館大学大学院先端総合学術研究科
『Core Ethics』Vol.12 2016年
論文
ストレングスモデルにおけるリカバリー概念の批判的検討
伊東 香純 pp. 1-11
PDF<336KB>
韓国の1980 年代における「浮浪人」という概念の創出と変化
――「兄弟福祉院事件」を中心に――
林 徳栄 pp. 13-24
PDF<547KB>
レイフ・ヴォーン・ウィリアムズの国民音楽観
――フォークソングによるイングランド国民性の表出――
奥坊 由起子 pp. 25-36
PDF<366KB>
在宅看取りという「選択」
――介護の場の意思決定過程をめぐる事例分析――
桶河 華代 pp. 37-49
PDF<430KB>
「処遇困難者専門病棟」新設阻止闘争の歴史
――精神障害者の社会運動の視角から――
桐原 尚之 pp. 51-61
PDF<374KB>
ろう児のためのフリースクール「龍の子学園」開校とその展開
クァク・ジョンナン pp. 63-76
「生涯学習」の一環としての「国際化」の試み
――亀岡市の姉妹都市交流とオクラホマ州立大学京都校誘致の事例を中心に――
児嶋 きよみ pp. 77-88
PDF<437KB>
精神障害当事者の語りがもたらす社会変革の可能性
栄 セツコ pp. 89-101
PDF<424KB>
日本における新生児マス・スクリーニングの導入
――「保因者」の発見と「出生防止」に着目して――
笹谷 絵里 pp. 103-114
PDF<404KB>
自律的参画へのプロセス
――勤務評定闘争における「恵那人事協議会」の1957 年度の記録から――
篠原 眞紀子 pp. 115-129
PDF<781KB>
日本的インクルーシブ教育システムについての考察
――特特委員会審議での就学先決定における保護者の位置づけの変化に着目して――
柴垣 登 pp. 131-143
台湾における病院死の作法としての「助念」と葬送儀礼をめぐる制度化
鍾 宜錚 pp. 145-155
PDF<422KB>
だれが「当事者」なのか?
――「精神障害当事者研究」のために――
白田 幸治 pp. 157-169
PDF<376KB>
生活保護に代わる所得保障制度を実現しようとした試みとその意義についての一考察
――障害基礎年金の成立過程で障害者団体と研究者は何を主張したのか――
高阪 悌雄 pp. 171-182
PDF<417KB>
ハンセン病の薬の変遷の歴史
――1960 年代の長島愛生園の難治らいの問題を中心として――
田中 真美 pp. 183-196
PDF<434KB>
薬物依存症者の親たちの困難感
――自助グループにつながった親たちの語りより――
谷口 俊恵 pp. 197-209
PDF<445KB>
Kenneth Waltz のメタ理論的考察とその哲学的批判
椿井 真也 pp. 211-221
PDF<350KB>
女子大学におけるキャリア形成と課外活動との連関
――観光ホスピタリティ教育とレセプショニストクラブを事例に――
永田 美江子 pp. 223-236
PDF<466KB>
訪問看護ステーションにおける看護職の裁量の範囲の拡大と法的責任
中西 京子 pp. 237-248
PDF<513KB>
在職中に重度視覚障害となった教員の復職過程
――「辞める」から「続ける」への転換に焦点を当てて――
中村 雅也 pp. 249-260
PDF<366KB>
「生活保護バッシング」のレトリック
――貧困報道にみる〈家族主義を纏った排除〉現象――
中村 亮太 pp. 261-274
PDF<468KB>
三障害ワンストップをめぐる相談支援体制の再編
――大阪市の場合――
萩原 浩史 pp. 275-286
PDF<465KB>
公立小学校における在籍学級での二言語併用授業
――外国人児童の包摂と多文化共生教育の可能性――
馬場 裕子 pp. 287-302
PDF<581KB>
生活保護基準決定に関する厚生労働省への財務省の影響に関する検討(2001-2009)
――「物価スライド」および「水準均衡方式」において参照する所得階層を中心に――
三輪 佳子 pp. 303-315
PDF<373KB>
研究ノート
障害者の教育を受ける権利
――高校入学の教育権訴訟を事例として――
定藤 邦子 pp. 317-329
PDF<443KB>
ベネッセアートサイト直島における「直島らしさ」の形成をめぐって
髙見澤 なごみ・古田 賢・枝木 妙子・永井 彩子・後山 剛毅 pp. 331-341
PDF<537KB>
先端総合学術研究科では、内部質保証の一環として教育・研究の質の改善、向上のために専門分野別外部評価を実施しています。立命館大学内部質保証方針に基づき、第1期(2015年度)に続き第2期として2022年度に実施をしました。今回の外部評価結果でご助言いただいた各項目の改善にとどまらず、みなさまの期待にお応えできるよう、毎年度の自己点検・評価活動を通じて更なる改善・改革に取り組んでまいります。
領域
生命
職位
教授
専門
医療社会学
担当科目
プロジェクト予備演習III(生命)
プロジェクト演習(生命)
業績
※21年度以降の最新情報は、下記にリンクされている研究者学術情報データベースをご参照ください。
2020年度業績一覧
2019年度業績一覧
2018年度業績一覧
2017年度業績一覧
2016年度業績一覧
2015年度業績一覧
研究者学術情報データベース
院生代表者
- 古田 賢
教員責任者
- 千葉 雅也
企画目的・実施計画
本研究会は服飾(ファッション・民族衣装・コスチュームなど)を表象文化の観点から研究することを目的としている。構成員の研究領域は服飾研究のみならず、ゲーム、スポーツなど多岐にわたっており、服飾について多角的な検討が可能となる。また、服飾文化を研究テーマにしているメンバーも服飾以外の知見を得ることができ、構成員各自の研究にも成果がフィードバックされることが期待できる。これらの研究会活動によって表象文化研究に対して服飾という視点から貢献ができる。加えて、構成員の半分以上が1回生であり、様々な学問分野に授業以外で触れることができる利点もあるという理由から企画した。
研究会活動は月に1回のペースで計10数回行う。構成員の研究関心に沿った研究発表を行い、ディスカッションを通じてメンバーの知見を高め、自身の研究分野とファッションを結び付けたテーマを設定する。最終的には2015年2月頃に研究報告発表会を開催し、学内および学外から参加者を募り、各自が研究成果を公表することを目標とした。
活動内容
初回はアクロス編集室『ストリートファッション 1945-1995―若者スタイルの50年史―』(1995)、城一夫・渡辺直樹『日本のファッション―明治・大正・昭和・平成―』(2007)、渡辺明日香『ストリートファッション論―日本のファッションの可能性を考える―』(2011)などを用いて日本の服飾文化を紹介した。次に各自の関心を探るため、代表者以外のメンバーが発表を行い、その発表内容を考慮して代表者は研究会活動を行うにあたり、ゲームやスポーツなどとファッションを関係付けたテーマを毎回設定してディスカッションを行った。目標としていた年度末の研究会発表では、外部からの参加者も招き、先端研内で行った。
研究会発表:「服飾文化×野球×ゲーム―方法論の模索と展開―」
日時:2015年2月5日(木)14:00~17:00
場所:創思館401・402
コメンテーター:千葉 雅也
古田 賢「日本におけるコスプレ受容の拡大―1990年代を中心に考察―」
根岸 貴哉「ユニフォームの機能と制約」
枝木 妙子「型友禅における野球柄」
ショウ ガン「デジタルゲームに含まれるファッション的要素」
シン ジュヒョン「現実のファッションを装うゲームのキャラクター―リアルからゲーム、ゲームからリアル―」
成果及び今後の課題
研究会活動についてはディスカッションや研究会発表、また、そのリハーサルを含め、今年度は10回以上行うことができた。研究会発表については、各自のテーマに他メンバーの研究領域からの知見を加えることができ、研究会の企画段階から想定していた「服飾について多角的な検討」を行うことができた。本研究会は来年度の継続も考えており、次回の研究会発表は規模を拡大し、今回以上に参加者を募りたい。
今後の課題として、今年度はディスカッションを中心としたため、研究会発表の準備にあてる時間が少なかったため、継続した場合は研究会発表に向けての発表を中心に行いたい。
院生代表者
- 鹿島 萌子
教員責任者
- 竹中 悠美
企画目的・実施計画
本プロジェクトは美術史に関する文献の講読を通して先行研究をマッピングすることで、研究に必要となる基礎的・理論的知識を身につけることを目的としたものである。プロジェクトメンバーの専門分野は多岐にわたるが、共通して知識を必要とする分野に芸術学・美術史がある。しかし、これまで各自で自身の研究を進めてきたため、土台となる基礎的知識にバラつきがみられ、各研究分野への深い理解が困難だという問題点があった。そこで本プロジェクトにおいて基礎的・理論的知識に基づく共通理解を身につけることで、参加者の研究分野を互いに理解し、活発な議論を行うことを目標とした。本プロジェクトは、芸術学の基礎的な知識を得る場をつくることに意義を持つものであった。
研究会の内容は二つに分けられる。一つは、メンバーによる報告を中心とした研究会の開催である。所属メンバーは美術館でのインターンシップや自主企画展に携わっている。そこで各メンバーの実践の報告をもとに、これまでの美術界の動向や現在の芸術学等における批判・問題点を立体的にとらえることを目指した。もう一つは、美術館の展覧会への見学会の開催である。実際に展示を見ることで、展示における作品の意味や社会性・政治性、あるいは展覧会のキュレーション方法について考える機会を得た。以上を通じ参加者は自身の見識を深め、各々の研究の深化・発展に繋げていくことを行った。
活動内容
■研究会
◆第1回研究会
日時:10月7日(火)場所:創思館4階 412号室
報告:高見澤なごみ
「国立国際美術館・インターンシップ報告―「ノスタルジー&ファンタジー 現代美術の想像力とその源泉」展を中心に―」
◆第2回研究会
日時:10月14日 場所:創思館4階 412号室
報告:古田賢「伝統工芸の展示考案―展示における「伝統工芸」と職人が語る「伝統工芸」―」
◆第3回
日時:10月28日 場所:創思館412
報告:枝木妙子「京都国立近代美術館学習支援事業「美術館の放課後」」
◆第4回研究会
日時:2015年1月13日 場所:創思館4階 412号室
報告:永井彩子(文学研究科文化情報学専修)「展示と演劇―近年の動向から―」
◆第5回研究会
日時:2015年2月27日 場所:創思館4階 412号室
報告:高見澤 なごみ「絵画作品のキャプションについて―大塚国際美術館を中心に―」
永井 彩子「複製技術の展示について」
枝木 妙子「ジャポニスムを取り扱った展示について」
古田 賢「「デュフィ展」の服の展示について―画家デュフィとファッション・デザイナーポワレの関係―」
■美術展見学会
◆第1回見学会
日時:10月25日
見学地:京都国立近代美術館「ホイッスラー展」、京都市美術館「ボストン美術館展」、記念講演会「ニューイングランドの港町と日本趣味―ボストン美術館の東洋美術収集はジャポニスムといかに交わるか-」(稲賀繁美氏)
◆第2回見学会
日時:11月30日
見学地:名古屋ボストン美術館「美術する身体-ピカソ、マティス、ウォーホル」展、名古屋市美術館「ゴー・ビトウイーンズ:こどもを通して見る世界」展、愛知県美術館「デュフィ展」
◆第3回見学会
日時:2015年1月18日
見学地:大塚国際美術館
成果及び今後の課題
本研究会は当初美術史の基礎的論文の講読を中心に行う予定であった。しかし、参加メンバーの多くがインターンシップ等で美術館・美術展に携わっていたことから、文献講読ではなく実践報告へと変更し、先行研究の知見を踏まえたうえで、各メンバーの立場から見えてくる美術展あるいは美術館の実践のありようについて報告した。また見学する美術展に関しても当初は近畿一円の美術展を予定していたが、愛知県・徳島県などの美術館へと変更した。通常容易にはいけない美術館の展覧会を見に行くことで、関西県下の美術展からは見えてこないキュレーションの方法や普及活動について考える機会とした。
その結果、大きく二つの成果を得ることができた。一つは、インターン等のメンバーの経験を共有したうえで、複眼的な思考のもとディスカッションを行うことができたことである。特に最後の研究会では、同一の展覧会を鑑賞しているにも関わらず注目するポイントが異なったことが如実に現れる結果となった。このことは、今後メンバーがキュレーションを手掛ける際に活かされるであろう。他研究科院生の参加があったことも、これまで出てこなかった新しい視点からの報告・意見が聞け、ディスカッションの幅を広げる結果となった。もう一つは、実際に展覧会に足を運んだことは、展示方法の考え方から来場者への配慮、またギャラリートークの工夫等を考える機会となった。メンバーのなかには今年度展覧会運営を行った者もおり、その際の展示デザインやトークの方法に活かされる結果となった。
今年度の研究会を通して得られた知見を、各メンバーの論文等に活かしていくことが今後の課題である。
構成メンバー
鹿島 萌子(表象領域・2008年度入学)
古田 賢(表象領域・2014年度入学)
枝木 妙子(表象領域・2013年度入学)
髙見澤 なごみ(表象領域・2014年度入学)
院生代表者
- 住田 安希子
教員責任者
- 小泉 義之
企画目的・実施計画
本研究会は、人の生命(生死)をめぐる問題に関する先行研究を取り上げ、倫理的観点から検討することを目的としている。研究活動をはじめて7年目になった今年度は、学会発表やジャーナルへの投稿を目標にし、各々の研究を進捗させる一つの拠点として研究会を位置づけ活動を行なっていったとともに、博論執筆中のメンバーの研究発表を合わせて積極的に実施した。こうした他者との議論を通じて、新たな方法論が展開されることも考えられる。ここに、本研究会の存在意義があるといえよう。
活動内容
◆日時、場所:2014年8月25日、14:30-17:30、学而館202
内容:鍾宜錚「台湾における『終末期退院』の慣行から捉えた治療中止の法と倫理」
西沢いづみ「住民との医療実践に取り組んだ医療者たちの役割?―京都・白峯診療所設立から堀川病院の初期活動までを対象に」
小西真理子「ケアの倫理に内在する自立主義―共依存概念を媒介にして―」
◆日時、場所:2014年10月20日、12:00-16:30、アカデメイア21、3階会議室
内容:鍾宜錚「台湾における終末期医療の議論と『自然死』の法制化?―終末期退院の慣行から安寧緩和医療法へ」
利光惠子「戦後日本における障害者への強制不妊手術に関する研究」
由井秀樹「日本における不妊医療研究の系譜」
小門穂「生殖補助医療規制の構築における『子どもを持ちたいという欲望』」
◆日時、場所:2015年3月26日、14:00-18:00、学而館202
内容:坂井めぐみ「戦中・戦後の日本における脊髄損傷の医療史」
篠原真紀子「『障害児』担当教師が実践した『私の教育課程』から見えてくる一人一人と集団形成―オリジナル作成の『教育課程表』と実践実感を綴った『私の教育方針』より―」
安田智博「イリイチの『脱学校の社会』について」
年度総括
今年度は計3回の研究会を行なった。その内容は主に各自の研究の進捗状況を発表し、議論し、その後の学会発表や論文執筆に有用な視座が与えられた。研究会で他者の発表を聞くことで、参加者も刺激を得ることができた。
今後も引き続き参加者が相互に刺激を与え合い、各々の研究を進捗させる一つの拠点として研究会を位置づけていきたい。
構成メンバー
住田安希子(代表者)
鍾宜錚
徳山貴子
馬場久理子
西沢いづみ
坂井めぐみ
伊藤岳史
※本研究科院生のみ記載
院生代表者
- 北村 隆人
教員責任者
- 千葉 雅也
企画目的・実施計画
本研究会は、フロイトやその他の精神分析学者の理論解釈と、その解釈を通じてメンバーの研究をさらに深めることを目的としている。研究会は、精神分析という学問において共通関心をもっているが、領域、専門分野および研究テーマは多様なメンバーで構成されている。研究会メンバーの多様な視点を通じて、様々な観点(精神分析の専門家、現代の社会学、哲学、文学)から精神分析における興味関心・問題意識を深めたり共有したりすることができる。
2014年度は二か月に一度のペースで研究会を開催する。活動は大きく分けて二部からなり、第一部ではフロイトの翻訳版テクストの講読を行い、第二部ではメンバーの学術的関心に即したフロイト以降の精神分析学者(フェレンツィ、アーブラハムなど)のテクストの講読および報告を行う。各テクストに精神分析の専門家による解説が行われ、テクストの講読および関連する研究報告を行う。また、精神分析に関係する他の研究会にも参加し、それに関する議論・意見交換も行う。
活動内容
◆第9回研究会
4月15日(火) 13時~ @生命部屋
『フロイト全集 17巻』
論文「集団心理学と自我分析」
ⅠⅡⅢ:北村隆人
ⅣⅤⅥ:馬場久理子
◆第10回研究会
6月10日(火) 13時~ @生命部屋
『フロイト全集 17巻』
論文「集団心理学と自我分析」
ⅦⅧⅨⅩ:小西真理子
『フロイト全集 14巻』
論文「喪とメランコリー」:馬場久理子
◆第11回研究会
9月2日(火) 13時~ @生命部屋
フェレンツィ『精神分析への最後の貢献』
フェレンツィ解説:北村隆人
論文「大人と子どもの間のことばの混乱」:小西真理子
論文「精神分析における積極技法のさらなる拡張」:馬場久理子
◆第12回研究会
11月18日(火) 15時30分~ @生命部屋
『アーブラハム論文集』
アーブラハム解説:北村隆人
論文「校門性格の理論のための補遺」:上尾真道
◆第13回研究会
1月20日(火) 15時30分~ @生命部屋
『アーブラハム論文集』
論文「心的障害の精神分析に基づくリビドー発達史試論」
前半(pp19-60):馬場久理子
後半(pp60-97):小西真理子
◆第14回研究会
3月17日(火) 15:30~ @生命部屋
メラニー・クライン解説:北村隆人
「精神分析と倫理」研究会概要:上尾真道
成果及び今後の課題
今年度は二か月に一度のペースで研究会を開催し、フロイトの著作(初期)の読解およびフロイト以降の精神分析理論に関する個人発表を中心として活動してきた。テクストはメンバーの学術的関心に即したものおよび各精神分析家の主要論文を取り上げた。一年間の活動を通じてメンバーが精神分析理論における基礎知識を習得したのちに、フロイト以降の精神分析の知識と理解を発展させ、個人研究にさらなる還元をすることができた。
今年度はメンバーの学術的関心に即した精神分析理論の著作を取り扱ってきたが、来年度はメンバーの個人研究に関連するより多くの精神分析学者の理論を取り上げ、精神分析の知識をより体系的に習得できる活動を行っていきたい。
構成メンバー
北村 隆人 公共領域 5回・2012年度入学
馬場 久理子 生命領域 5回・2010年度入学
院生代表者
- 山口 隆太郎
教員責任者
- 竹中 悠美
企画目的・実施計画
本プロジェクトの目的は、ガダマー『真理と方法』の講読を通して、芸術経験や作品について論ずる際の解釈学的方法論を理解することであった。ガダマーの解釈学は20世紀ドイツにおける主要な芸術哲学であり、様々な芸術実践を例に作品の存在論を展開している。彼の解釈学的方法を理解することにより、構成員各自がそれぞれ研究対象にしている諸芸術に応用して、各自の研究を発展させることができると考えた。
本プロジェクトでは、昨年度に引き続き、講師として大阪歯科大学の石黒義昭先生を招聘して、助言を得ながらHans-Georg Gadamer; Wahrheit und Methode: Grundz?ge einer philosophischen Hermeneutik, J.C.B. Mohr, 1960(『真理と方法Ⅰ』轡田収他訳、法政大学出版局、1986)を原文に基づいて読解し、理論的背景の把握および主要な概念を理解することを目指した。また、構成員各自の研究課題にそった研究発表を行うことも予定した。
活動内容
・第一回研究会
日時:2014年7月19日(土)14時00分から18時00分
場所:朱雀キャンパス312号室
内容:石黒先生を招聘して、邦訳145頁から154頁を輪読し、関連する論点を議論した。
・第二回研究会
日時:2014年10月26日(日)14時00分から18時00分
場所:朱雀キャンパス313号室
内容:石黒先生を招聘して、邦訳154頁から166頁を輪読し、関連する論点を議論した。
・第三回研究会
日時:2014年12月8日(月)17時30分から20時30分
場所:衣笠キャンパス 創思館406号室
内容:これまでの講読箇所および関連するテーマについて議論した。鹿島がこれまでの要点について、高見澤が重要概念である「ミメーシス」について、報告した。根岸貴哉(表象領域)が「シラーの「遊戯」論」と題した報告を、焦岩(表象領域)がホイジンガの遊戯論を紹介し、ガダマーの「遊び」概念との比較がなされた。山口はガダマーが例示する演劇に関連して、「ギリシア悲劇からオペラへ」と題した報告を行った。
・第四回研究会
日時:2014年12月14日(日)14時00分から18時00分
場所:朱雀キャンパス312教室
内容:石黒先生を招聘して、邦訳166頁から175頁を輪読し、関連する論点を議論した。
・第五回研究会
日時:2015年2月16日(月)14時00分から18時00分
場所:朱雀キャンパス312教室
内容:石黒先生を招聘して、2月21日の研究会に向け、山口の発表草稿「アルフレッド・シュッツの音楽論における音楽経験――音楽作品・時間・リズム」を検討した。
・第六回研究会(文芸学研究会第57回研究発表会との共催)
日時:2015年2月21日(土)13時30分から18時00分
場所:朱雀キャンパス304教室
内容:山口「アルフレッド・シュッツの音楽論における音楽経験――音楽作品・時間・リズム」、里中俊介(大阪大学)「プラトン「詩人追放論」における快の問題」、竹中悠美「1930年代アメリカの災害表象における文学的救済と写真的呵責」の各発表が行われた。
成果及び今後の課題
本プロジェクトの成果として次の二点が挙げられる。第一に、ガダマー解釈学における基礎的な考察箇所を講読し、①「遊びSpiel」概念から芸術経験への橋渡しとして「観衆」が必要であること、②芸術作品とその経験という二分法ではなく、経験を媒介に浮かび上がってくる作品存在を考察すること、これらがガダマーの根底となる立場であることが確認できた。これらのことは、ガダマーが例示した演劇や音楽のみならず造形芸術においても重要な点であると思われるし、その点を随時ディスカッションすることができた。第二の成果として、講読で得た知見と関連するテーマを第三回および第六回研究会で議論することができたことが挙げられる。特に第三回研究会では、研究会構成メンバー以外の院生も参加し、「遊び」概念の広がりについて考える機会となった。
丁寧な読解と活発な議論が行われた反面、講読のスピードが遅かった点は反省すべきであろう。だからといって、やみくもに速く読むことが良いとは思われない。今年度の反省をふまえつつも、これまでの長所を無くさずに、解釈学の核心に迫るべく講読を続けていきたい。
構成メンバー
山 口 隆太郎(表象領域・2013年度入学・代表者)
鹿 島 萌 子(表象領域・2008年度入学)
川 﨑 寧 生(表象領域・2008年度入学)
角 田 あさな(表象領域・2008年度入学)
高見澤 なごみ(表象領域・2013年度入学)
院生代表者
- 荒木 慎太郎
教員責任者
- 吉田 寛
企画目的・実施計画
本研究会の目的は映画・マンガ・アニメなど様々な作品と現実世界に存在するフィクションに着目し、その技術や役割に注目し比較検討することにある。映画中に見られる未来の技術の「ハイテクノロジー」と、現在の現実世界・映画中の技術における「ハイテクノロジー」とは大きく異なる。また、映画中に登場したデバイスの中には、バック・トゥー・ザ・フューチャーに登場したコンピュータに接続可能なメガネの様に現在のGoogle GlassやOculus Riftの様な技術の前身の技術と言えるほど酷似しているものも存在する。各時代、様々な媒体のフィクションに登場する技術を比較検討し、その特徴・傾向に関する理解を深めながら「フィクションとテクノロジー」の様々な相互関係を考える。
活動内容
第1回研究会:2014年6月27日
東京ビッグサイトで行われた商業展示会「3D&バーチャルリアリティ展」に参加し、現在の最新技術に対する見識を深め、情報収集を行った。
第2回研究会:2014年7月2日
「3D&バーチャルリアリティ展」で収集した専門技術を分類し、リストを作成。今後の活動方針の検討を行った。
第3回研究会:2014年9月3日
リアルとフィクションにおけるテクノロジーを比較するにあたり、80年代、90年代、00年代、に製作されたSF映画作品の「作中年代」「作品の内容」を調べ、リストを作成。今後の方針についての協議を行った。
第4回研究会:2014年10月15日
80年代、90年代、00年代に製作されたSF映画作品のジャンル、内容の分類を分担して行った。
第5回研究会:2015年3月
作中年代が2030年±10年の作品、アンドロイドやロボットなどのハイテクノロジーが描かれている作品を抽出し比較検討を行った。
成果及び今後の課題
本年度は研究会の立ち上げ年度ということで、各メンバーの興味関心を話し合い、研究会としての方針を固め、映画などのフィクションに見られるテクノロジーと現実世界における技術や理論を比較し、その差異や共通項を見出すこととした。3D&バーチャルリアリティ展に参加し、現実の技術力を確認し、1980年代から2000年代までの映画中に見られるテクノロジー描写をまとめ、それらと現実の技術を比較検討した。
今後は引き続き商業展示会に参加し、現実の技術の動向を追いながら、さらに幅広い検討を行いたいと考えている。また、本年度が研究会の立ち上げ年度ということで、メンバーとの連絡や連携において不備があった。次年度は今年度の反省をふまえた上で計画的に研究会を運営していきたい。
構成メンバー
荒木 慎太郎 先端総合学術研究科 表象領域
伊藤 京平 先端総合学術研究科 表象領域
伊藤 岳史 先端総合学術研究科 生命領域
モリ・カイネイ 先端総合学術研究科 共生領域