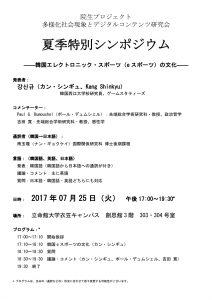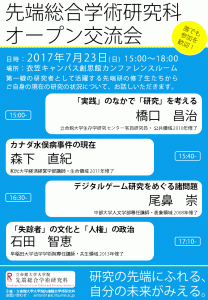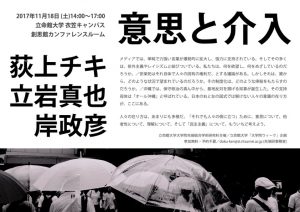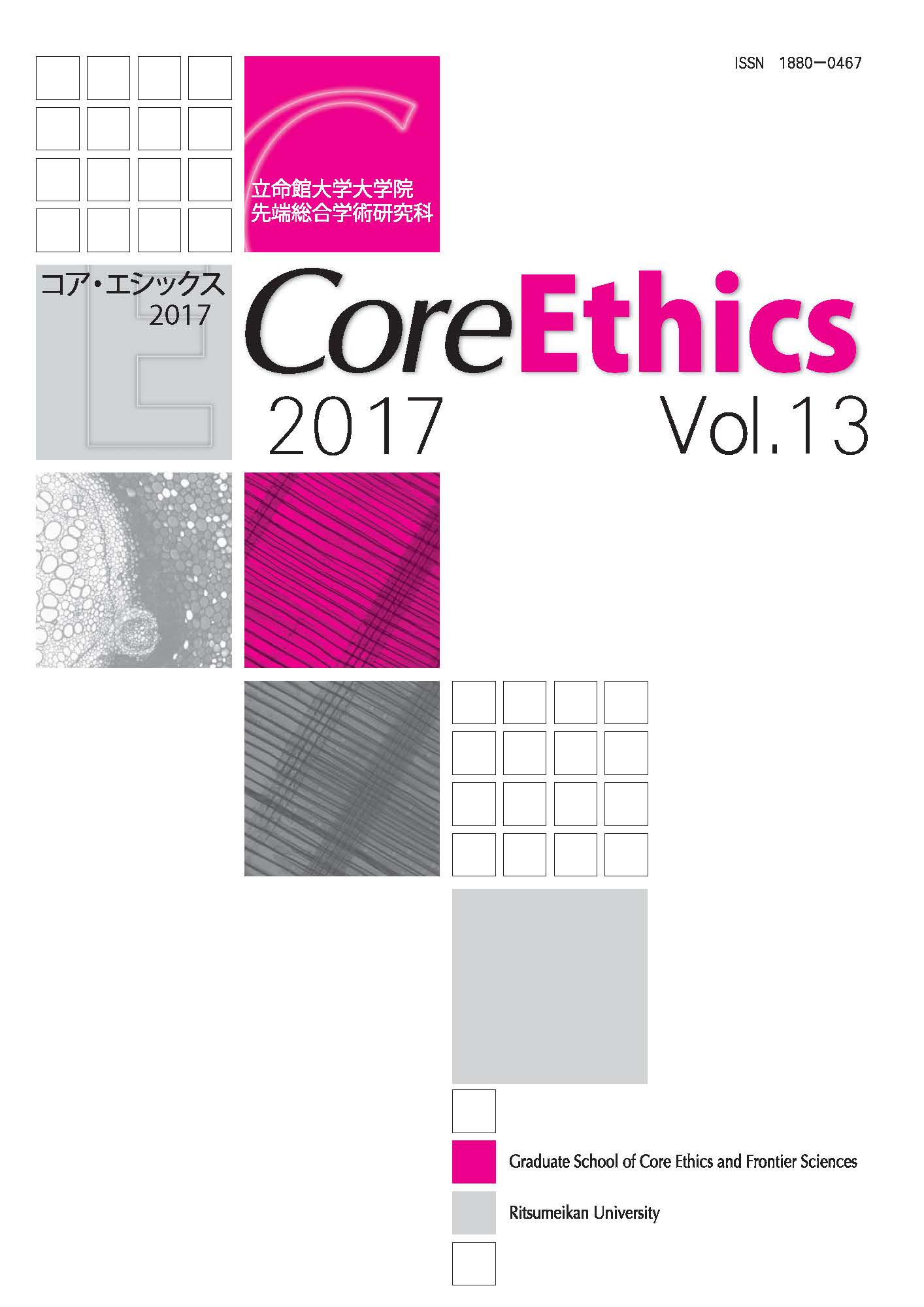院生代表者
- 向江 駿佑
教員責任者
- 小川 さやか
企画目的・実施計画
近年、一部で同性愛者同士の婚姻が認められたり、児童ポルノ関連法案が成立したりするなど、広く「性」をめぐる動きが活性化している。こうした動きはしばしば政治的な観点から論じられるが、我々が日々消費している表象文化に目を向けることでこそ、問題をより身近なものとして論じることができる。本プロジェクトは、初年度のテーマとして乙女・美少女カルチャーにおけるセクシュアリティとジェンダーの表象、とりわけ巨大な市場が存在しながら学術的研究が滞っている「乙女ゲーム」の文化的意義を主たる研究の対象とする。具体的には理論研究と資料分析のほか、現物や資料が集まる東西の拠点である、大阪日本橋の「オタロード」と東京池袋の「乙女ロード」でフィールドワークを行う。また本プロジェクトには学外研究者の参加も予定されているため、前後期で数回のワークショップをおこない、その成果を学会等で報告することを検討している。
活動内容
- 第一回フィールドワーク
日時:2016年6月12日
場所:大阪・日本橋
内容:大阪・日本橋の「オタロード」において乙女・美少女カルチャーについての調査
- 第一回公開研究会
日時 : 2016年7月14日
場所 : 究論館プレゼンテーションルームA
内容 : Tina Richards、Kristine Øygardsliaの両氏による報告とそれに基づく公開討論会
- 第二回公開研究会
日時 : 2016年10月25日
場所 : 究論館プレゼンテーションルームA
内容 : 愛知淑徳大の松井広志氏によるモノのメディア化に関する報告および夏季休暇中に行われた向江の欧州でのゲームスタディーズの調査報告
- 第二回フィールドワーク
日時 : 2016年12月24-25日
場所 : 東京・池袋、秋葉原など
内容 : 池袋と秋葉原を中心とした都内の乙女・美少女カルチャーについての調査
- 学会発表
日時 : 2017年3月12日
場所 : 名古屋・成城大学
内容 : 日本デジタルゲーム学会2016年度年次大会において向江・劉が報告(「乙女ゲームにおける慰めのストラテジー」)。
成果及び今後の課題
本プロジェクトは2016年度開始であり、本年度は「調査」の年であった。2度の公開討論会とフィールドワークを通じて得た知見を、学会発表などを通じて内外の研究者に共有するという一連の活動において、今日の表象文化におけるジェンダーとセクシュアリティをめぐる多様な言説がどのように生み出されるのかの一端を確認することができた。一方で、収集したデータの活用方法や体系化など、検討すべき課題も多い。今後はこうした調査によって得た知見を体系的にマッピングしていく「設計」、それをもとに理論構築とデータの公開を行う「集成」の各段階に向けて、場合によっては複数年度に渡る中長期的な計画を立案しつつ、今年度行なった調査に関しても継続して行っていく。
構成メンバー
向江 駿佑(表象領域・2015年度入学)
シン・ジュヒョン(共生領域・2014年度入学)
劉雨瞳(表象領域・2016年度入学)


.jpg)