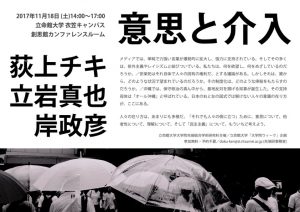日時・場所
日時:11月20, 21, 22, 24日 10:00-13:30
場所:立命館大学 衣笠キャンパス 創思館407教室
参加無料・要事前申込
講師
Dr. Fernando Vidal
フェルナンド・ヴィダル教授
(カタロニア高等研究所 ICREA /バルセロナ自治大学)
講義のテーマ
- Day 1 (Monday, 20 November)
“Body and person in Western Christianity” - Day 2 (Tuesday, 21 November)
“Brains, individuals, culture” - Day 3 (Wednesday, 22 November)
“Brain thought experiments and popular culture” - Day 4 (Friday, 24 November)
“Brain death, disorders of consciousness, locked-in syndrome”
Bynum and Vergote provide historical and conceptual background to the connection body-person in the Christian tradition. Locke, in the late 17th century, develops a new theory of personal identity; reading priority should be given to sections 6, 10 and 17-20. Ozawa proposes new ways, informed by Japanese thought, of thinking about the sociology of the body; her article serves as transition to the following class.
Main topic paper: Chikako Ozawa-de Silva
“Beyond the Body/Mind? Japanese Contemporary Thinkers on Alternative Sociologies of the Body”
Racine documents how functional magnetic resonance imaging (fMRI) is perceived in the public. O’Connor & Joffe review the evidence for an impact of “neuro” on lay views of personhood. Chiao et al. and Kawabata & Zeki are representative examples of the neuroscientific approach to important humanistic and anthropological issues.
Main topic paper: Eric Racine “fMRI in the public eye”
Puccetti and Dennett, two professional philosophers use thought experiments to explore the relationship of brain and personal identity; Dahl, a writer, does something very similar. Sconce explores the meaning of brain movies during the Cold War and Vidal explores how film rehearses the idea that we are essentially our brains.
Main topic paper: Roland Puccetti “Brain transplantation and personal identity”
The Harvard Report is the document that launches the definition of brain death in 1968. Bernat discusses controversies around brain death. Owen demonstrates that persons diagnosed as being in vegetative state can voluntarily modulate their brain activity and use that capacity to communicate. Nizzi et al. is an important questionnaire investigation on views about the self, held by persons with locked-in syndrome.
Main topic paper: Marie-Christine Nizzi “From armchair to wheelchair: How patients with a locked-in syndrome integrate bodily changes in experienced identity”
主催
立命館大学大学院先端総合学術研究科
お問い合わせ
参加希望の方は、事前にご連絡ください。
各日程のメインの論文は記載の通りですが、他にも推薦論文があります。
論文リスト全体は、メールでお問い合わせください。
連絡先:2017lecturevidal (at) gmail.com