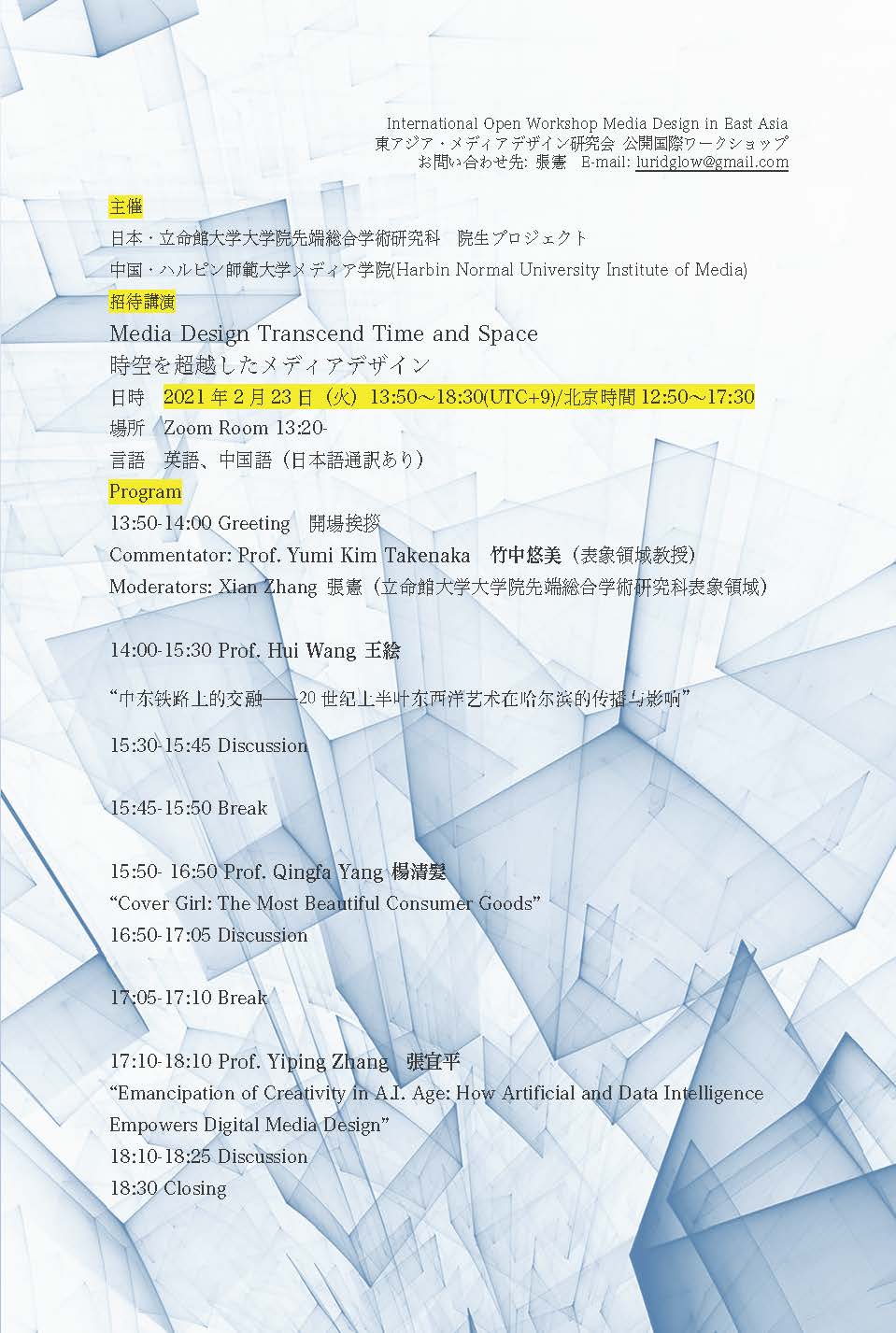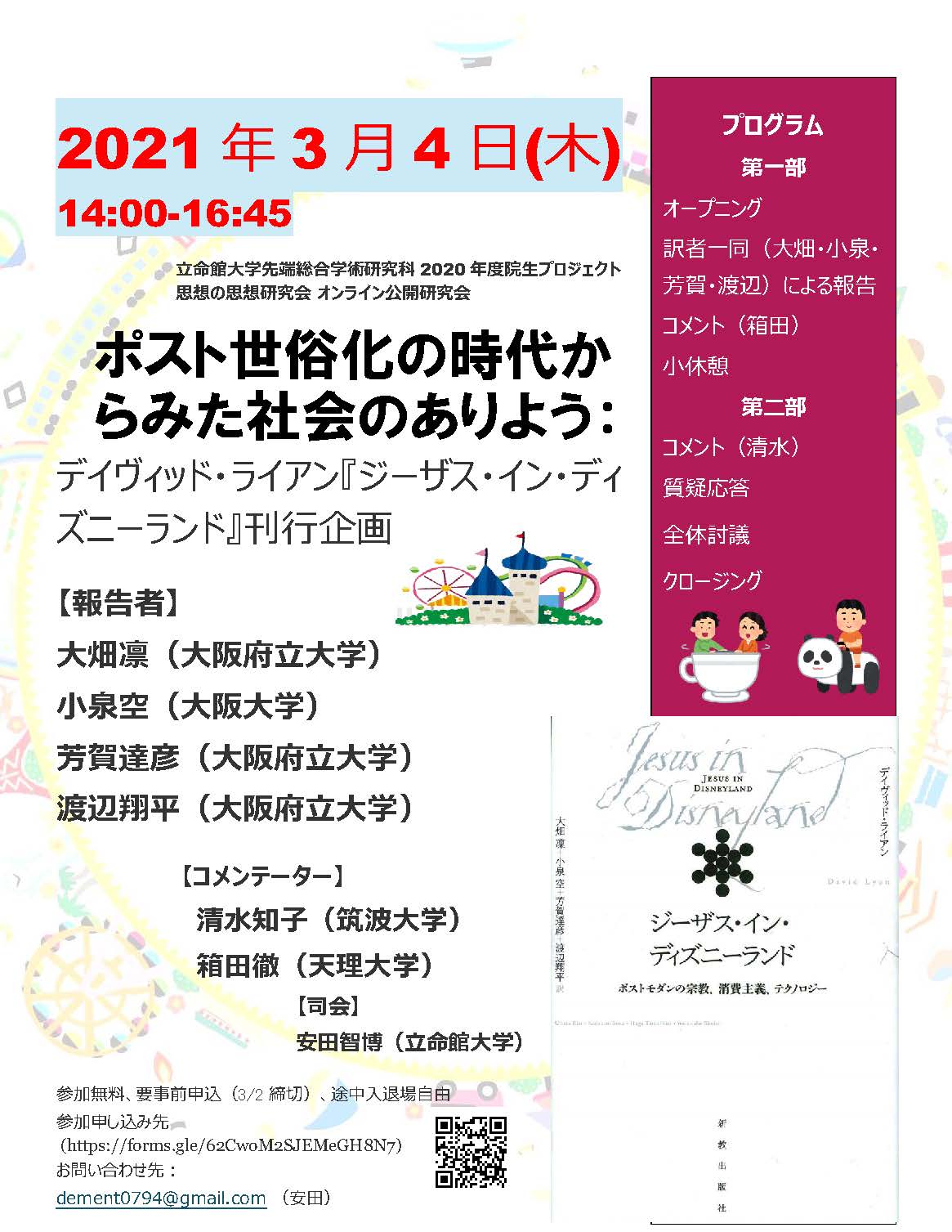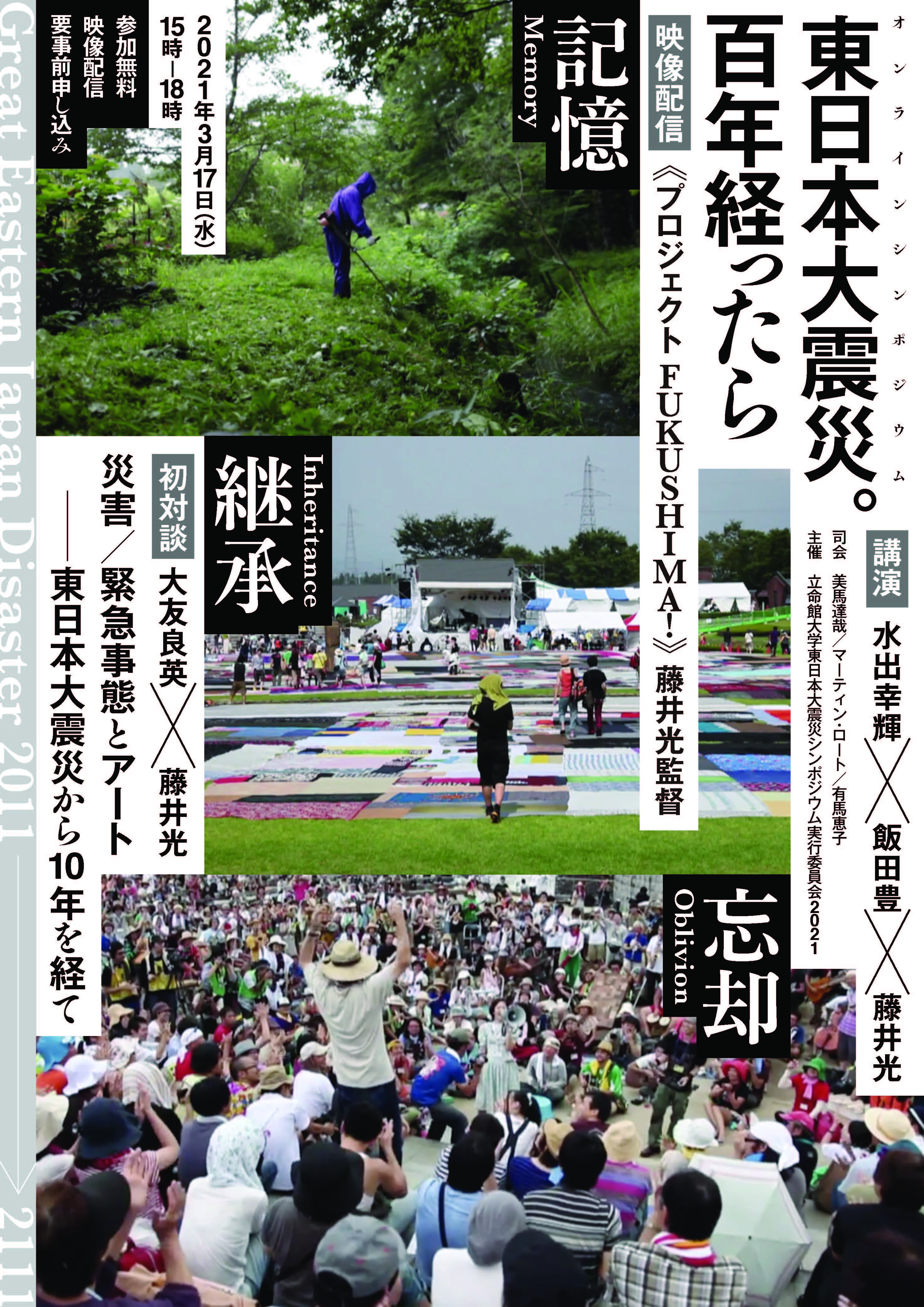書いたもの(論文その他)
単著論文(日本語)
■ 「研究不正からみえる科学の現代」
地盤工学会誌 67巻6号、2019年、p.p.54-9.
■ 「Locked-in state (LIS)・Minimally conscious state (MCS)・Vegetative state (VS)に関する最近の知見」
脳神経内科 91巻6号、2019年、p.p.665-73.
■ 「マイノリティ・アーカイブズの言挙げ」
立命館生存学研究 3巻、2019年10月p.p.3-5.
■ 「戦争/バイオポリティクス/障害」
福音と世界 2020年2月p.p.18-23.
■ 「医療社会学の冒険12 ケアの機械と人間主義」
医学のあゆみ 269巻3号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.247-250.
■ 「医療社会学の冒険13 難病の剰余価値」
医学のあゆみ 269巻8号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.619-23.
■ 「医療社会学の冒険14 患者運動が臨床試験を変える」
医学のあゆみ 269巻11号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.889-892.
■ 「医療社会学の冒険15 感染源としての患者」
医学のあゆみ 270巻3号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.279-282.
■ 「医療社会学の冒険16 脳死が映画になるとき」
医学のあゆみ 270巻8号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.666-669.
■ 「医療社会学の冒険17 ことばの映画 吃音を描く」
医学のあゆみ 270巻13号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.1241-1245.
■ 「医療社会学の冒険18 主人公はMR」
医学のあゆみ 271巻3号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.303-306.
■ 「医療社会学の冒険19 ヒステリーのヒストリーと19世紀健康ブーム」
医学のあゆみ 271巻 号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.683-686.
■ 「医療社会学の冒険20 人工呼吸器という家電」
医学のあゆみ 271巻12,13号(2019)、医歯薬出版株式会社、p.p.1327-1330.
■ 「医療社会学の冒険21 別の身体になること−――ウィッシュではなくニーズ」
医学のあゆみ 272巻3号(2020)、医歯薬出版株式会社、p.p.261-265.
■ 「医療社会学の冒険22 ソーマ(身体)はセーマ(墓)である」
医学のあゆみ 272巻8号(2020)、医歯薬出版株式会社、p.p.681-685.
■ 「医療社会学の冒険23 不死となった身体(の一部)」
医学のあゆみ 272巻12号(2020)、医歯薬出版株式会社、p.p.1236-1239.
共著論文(日本語)
■ 柴田純也、美馬達哉「tSMS(transcranial static magnetic stimulation)」Clinical Neuroscience 38巻1号(2020)中外医学社、36-8頁.
共著論文(英語)
■ Shibata S, Watanabe T, Yukawa Y, Minakuchi M, Shimomura R, *Mima T. (2020) Effect of transcranial static magnetic stimulation on intracortical excitability in the contralateral primary motor cortex.
Neuroscience Letters in press
doi: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134871
■ Tsuru D, Watanabe T, Chen X, Kubo N, Sunagawa T, Mima T, *Kirimoto H. (2020) The effects of transcranial static magnetic fields stimulation over the supplementary motor area on anticipatory postural adjustments.
Neuroscience Letters in press
doi: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134863
■ Shibata S, Yamao Y, Kunieda T, Inano R, Nakae T, Nishida S, Inada T, Takahashi Y, Kikuchi T, Arakawa Y, Yoshida K, Matsumoto R, Ikeda A, Mima T, *Miyamoto S. (2020) Intraoperative electrophysiological mapping of medial frontal motor areas and functional outcomes.
World Neurosurgery, in press
■ *Koganemaru S, Mikami Y, Matsuhashi M, Truong DQ, Bikson M, Kansaku K, Mima T. (2020) Cerebellar transcranial alternating current stimulation modulates human gait rhythm.
Neurosci Res. (査読有)
doi: https://doi.org/10.1016/j.neures.2019.12.003
■ Nojima I, Oliviero A, *Mima T. (in press) Transcranial Static Magnetic Stimulation -From bench to Bedside and Beyond-.
Neurosci Res. (査読有)
doi: https://doi.org/10.1016/j.neures.2019.12.005
■ *Kitatani R, Koganemaru S, Maeda A, Mikami Y, Matsuhashi M, Mima T, Yamada S. (in press) Gait-synchronized oscillatory brain stimulation modulates common neural drives to ankle muscles in patients after stroke: a pilot study.
Neurosci Res. (査読有)
doi: 10.1016/j.neures.2019.11.001.
■ *Satow T, Komuro T, Yamaguchi T, Tanabe N, Mima T. (in press) Transcranial Direct Current Stimulation for a Patient with Locked-in Syndrome.
Brain Stimul. 13(2):375-7.(査読有)
doi: https://doi.org/10.1016/j.brs.2019.11.007
■ *Maezawa H, Vicario CM, Kuo MF, Hirata M, Mima T, Nitsche MA.(in press) Effects of bilateral anodal transcranial direct current stimulation over the tongue primary motor cortex on cortical excitability of the tongue and tongue motor functions.
Brain Stimul. 13(1):270-2.(査読有)
doi: 10.1016/j.brs.2019.10.005.
■ Yamaguchi T, *Satow T, Komuro T, Mima T. (2019) Transcranial Direct Current Stimulation Improves Pusher Phenomenon.
Case Rep Neurol. 11(1):61-65. (査読有)
doi: 10.1159/000497284.
■ *Koganemaru S, Kitatani R, Fukushima-Maeda A, Mikami Y, Okita Y, Matsuhashi M, Ohata K, Kansaku K, Mima T. (2019) Gait-synchronized rhythmic brain stimulation improves post-stroke gait disturbance: a pilot study. Stroke 50(11):3205-12. (査読有)
doi: /10.1161/STROKEAHA.119.025354
ウェブ寄稿
■ 「実は世界中で行われていた「強制不妊」〜弱者に優しい福祉国家でも…」2019.5.6
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64409)
■ 「なぜ「超高価な新薬」が増えるのか? 知られざる「からくり」を解説 白血病の新治療薬は1回3000万円」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64849)
■ 「目の前の患者に優先順位をつける…「トリアージ」をめぐる諸問題 日本で現実的に問題になっていること」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65652)
■ 「子どもたちも依存…「エナジードリンク」飲み過ぎはどれほど危険か カフェイン中毒というリスク」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65981)
■ 「死亡で議論過熱…「電子タバコ」いま何が問題なのか 「グレー=悪」として叩く風潮」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67248)
■ 「論争は終わらない…「揺さぶられっ子症候群」と虐待のあいまいな関係 想像を絶する家族の苦悩と子どもの無念」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68391)
■ 「高齢者5人に1人が発症も…「認知症薬」に決定打が出ない理由 エビデンスと仮説が揺らいでいる」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69804)
■ 「中国発「新型肺炎」が生み出す大事態を恐れすぎてはいけない理由 患者は犠牲者か、それとも…」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69955)
■ 「新型コロナ「発症者続出の船内に閉じ込める措置」で社会防衛できるか 新型肺炎と検疫の神話」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70490)
■ 「新型コロナ「衝撃の休校要請」…多くの医師が疑問を抱いている 子どもたちにしわ寄せを強いる古い発想」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70710)
■ 「新型コロナ危機、日本政府の「対策」に抱いた恐怖 中国の接触者追跡99%が意味すること」
現代ビジネス(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71168)
■ 「脳神経科学の現在 意識を探す」
RAD-IT21(https://rad-it21.com/ai/tatsuya_mima20200107/)
書評
■ 「『伝わってしまう歴史』に抗う」(田中祐理子『病む、生きる、身体の歴史』青土社)週刊読書人2019年9月13日
話したこと(講演その他)
■ “Rethinking Medicalization in the Context of Bioethics”, Uehiro-Carnegie-Oxford Annual Conference 2019: Rethinking Bioethics for the 21st Century, St Cross College, Oxford, UK. May21-2, 2019.
■ 灘高校 高校生のための土曜講座「神経科学の最先端 生きた人間の脳を刺激する」、灘高校、神戸市、2019年6月8日
■ 灘高校 高校生のための土曜講座「生命倫理の最先端 治療を超えたエンハンスメント(増強)は許されるか」灘高校、神戸市、2019年6月8日
■ “Japanese Welfare State: From Total War System to Globalization”, International Comparison and Collaboration in Medical Sociology: Research Initiatives, Challenges, and Future Prospects. Cardiff University, Cardiff, UK. 20th Aug. 2019.
■ “Rethinking medicalization in the bioethics of 21st century”, International Society for Clinical Bioethics XVI Annual Conference. Krakow, Poland. 4th Oct. 2019.
■ “Effects of static magnetic fields in stroke rehabilitation”, Seminarios de la unidad de investigacion. Hospital Nacional de Paraplejicos. Toledo, Spain. 11th Oct, 2019.
■ 「新しい脳刺激法:静磁場刺激を中心に」、シンポジウム13脳刺激法の現在―基礎から臨床へ―、第49回日本臨床神経生理学会学術大会、2019年11月29日、ザ・セレクトン福島
■ 「ネオ・リハビリテーションを目指す非侵襲的脳刺激法」、第24回日本基礎理学療法学会学術大会、2019年11月30日、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター
■ 「新しい脳刺激によるネオ・リハビリテーション」、九州大学医学研究員生態情報科学ゼミ、2020年1月14日、九州大学
■ 「新しい非侵襲的脳刺激法とリハビリテーション」、広島大学医系科学研究科FD講義、2020年1月15日、広島大学
■ “Closed-loop system for gait-synchronized brain stimulation can improve post-stroke gait disturbance”, poster presentation, IBRO Workshop. Szeged, Hungary. 29-30 Jan, 2020.
学会における主な活動(所属学会・現在務める委員等)
【所属学会】
■日本保健医療社会学会
■日本生命倫理学会
■日本神経学会
■日本神経科学会
■日本臨床神経生理学会
■日本リハビリテーション学会
■Society for Neuroscience
【学会での活動】
■日本生命倫理学会・評議員
■日本臨床神経生理学会・代議員
■日本生体磁気学会・理事
関連企画・研究会
■国際シンポジウム「共有できない平和/争いが移動する」International Symposium “Unshareable Peace(s) / Conflicts in Motion”、 立命館大学衣笠キャンパス 創思館カンファレンスルーム、2019年11月9日