院生代表者
- 荒木 慎太郎
教員責任者
- 竹中 悠美
概要
本研究プロジェクトは、近年研究され始め、活発に研究されるようになったテレビドラマに焦点を当てる。
テレビドラマ制作の技術がどのように映画から受け継がれ、またテレビドラマが独自の価値を獲得し映画とは違うものとして成立していくのかを検討し、映画・テレビドラマを脚本や監督・演出といった制作の面から分析する能力を向上させることを目的とする。
本研究会は映像作品を鑑賞しディスカッションを行うことが基本的な様式となるが、ゲスト講師を招聘し、専門的な分野からの意見とご教授をいただくことで、映像作品を理論・実践の面から検討する。ゲスト講師は映画美学と映画実践に精通する大阪大学名誉教授の上倉庸敬先生を予定し、制作分野など他のゲスト講師の方にも交渉中である。
また、京都という都市は映画と縁深く、東映撮影所を始めとする撮影所と撮影地が多く存在する。近年は実写だけでなくアニメにおいても京都は多く描かれており、映像作品における京都の価値は大きい。映像作品の検討に加えて、撮影所や撮影地に行き、実際に目で見て観察することで、切り取られた映像の中の京都と実際を検討することも行いたい。
本研究会の意義は、映画とテレビドラマを、脚本や監督の作風といった制作の面から検討することであり、実際に撮影所や撮影地に行ってシーンやカット、ショットを検討する試みは新たなディスカッションの糸口となるのではないか。
活動内容
第一回研究会
日時:2022年8月19日(金)16時~19時
場所:創志館312
内容:上倉庸敬先生(大阪大学名誉教授)を招聘し、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』第一章の読書会を行った。継続して購読を行うために、整理を行いながら、第一章の精読を行った。
第二回研究会
日時:2022年9月16日(金)16時~19時
場所:創志館312
内容:上倉庸敬先生(大阪大学名誉教授)を招聘し、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』第一章の読書会を行った。ボードウェルの指摘する、日本らしさ、革新性についての理解とディスカッションを行い、上倉先生にご教授をいただいた。カットの比較検討も行い、家屋の奥まで詳細に映されるショットや「触れる」という主題の重要性が浮かび上がった。
第三回研究会
日時:2022年10月28日(金)16時~19時
場所:創志館312
内容:上倉庸敬先生(大阪大学名誉教授)を招聘し、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』第二章の読書会を行った。ボードウェルの指摘する、日本らしさについての検討を行った。小津安二郎は保守的な監督なのか、革新的な監督なのか、ボードウェルの小津論を読み進めながら、上倉先生にご教授をいただき、小津映画についての理解と、ショットについての理解を深めた。
第四回研究会
日時:2022年11月18日(金)16時~19時
場所:創志館408
内容:上倉庸敬先生(大阪大学名誉教授)を招聘し、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』第三章の読書会に向け、小津安二郎監督『戸田家の兄妹』(1941)を視聴し、ディスカッションを行った。ボードウェルの指摘する日本らしさについての検討を行っていくために、上倉先生にご教授をいただき、小津映画とショットについての理解を深めた。
第五回研究会
日時:2022年12月16日(金)16時~19時
場所:創志館408
内容:上倉庸敬先生(大阪大学名誉教授)を招聘し、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』第二・三章の読書会を行った。映画のスタイルと構造を中心に、映画を参照しながらディスカッションを行った。ボードウェルの指摘する規範や評価について、上倉先生にご教授をいただき、小津映画とショットについての理解を深めた。
第六回研究会
日時:2023年2月28日(金)11時~18時
場所:創志館408
内容:メンバーの関心のある作品や、研究対象となる映像作品を持ち寄り、鑑賞会とディスカッションを行った。映画『パルプ・フィクション』(1994) など、名作を改めて見ることで新たな気付きと議論が生まれた。また、テレビドラマ『スケバン刑事』(1985)を大画面で見ることで、テレビサイズというスクリーンに収めるための横幅の狭さを強く感じるとともに、そこから生じるセットの問題や、作られたショットの違和感についてもディスカッションを行った。
成果及び今後の課題
本研究会を通じて、デヴィット・ボードウェル『小津安二郎 映画の詩学』で論じられている映像論(小津論)について理解を深めることができ、カットやショットに込められた意味を見つけ、それらに対する理解を深めるための貴重な機会となった。読書と合わせて、映像作品の鑑賞を行うことで、映像の持つ「感じる」という感性と物語の関係性を改めて認識し、理解を深めることができた。
映像理論の理解を深めることに重点を置いたため、計画していた撮影所に行き、実際にシーンやカットを検討することはできなかった。メンバーの意見を取り入れながら、映画・テレビドラマという垣根にとらわれず、理解を深めることを目的とし、一定の成果を得られたが、メンバーそれぞれが、自身の研究分野と映像文化の関係性をより明確化し意識していくことで、研究会の質の向上が期待できると感じた。今後はメンバーの研究内容についても意見交換を行い、理解を深めながら、映画・テレビドラマについての理解を深め、実践も行えるように運営を行っていきたい。
構成メンバー
荒木 慎太郎
濱中 健太
嶋津 麻穂
西川 秀伸
宮内 沙也佳
張 芸馨


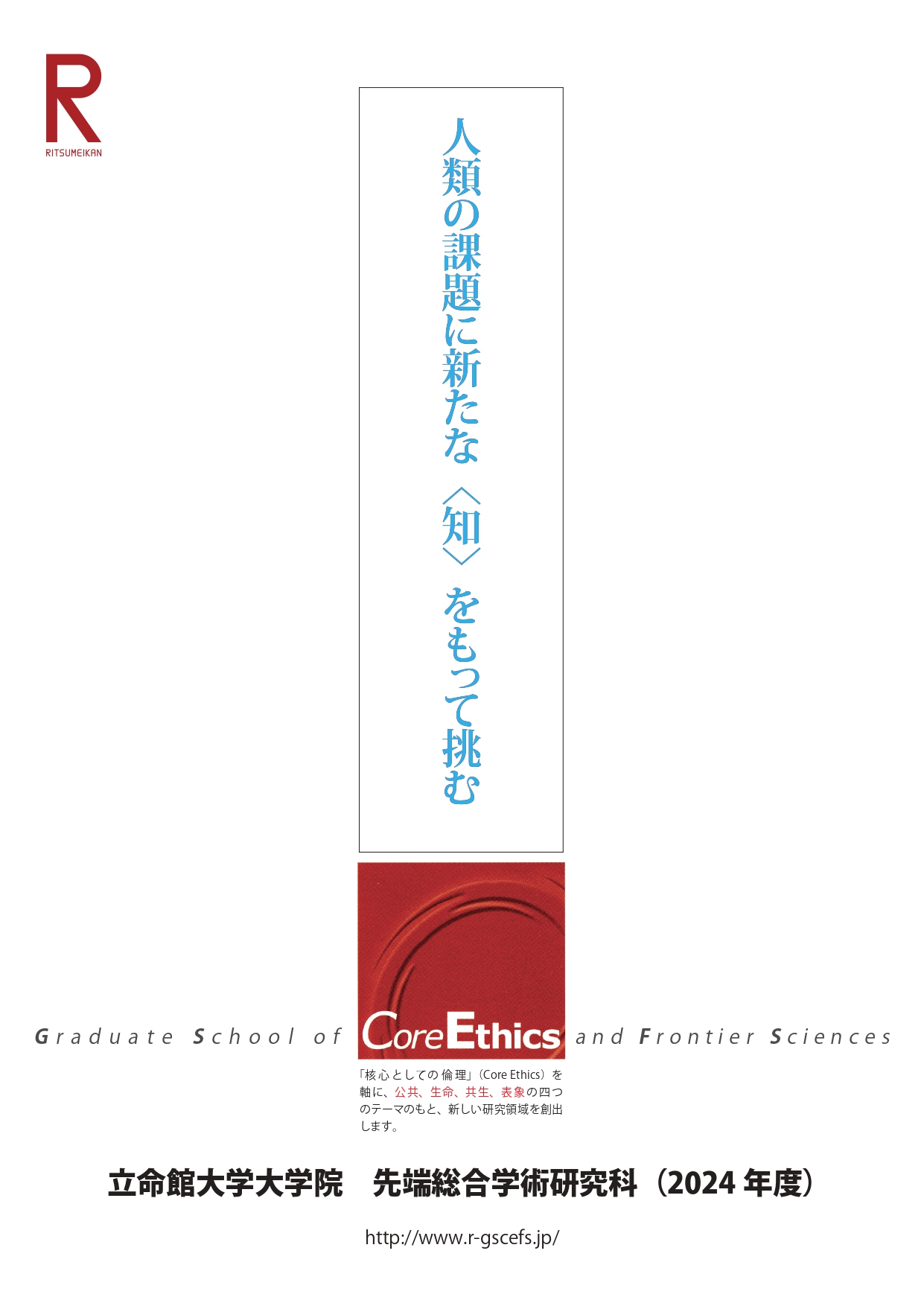
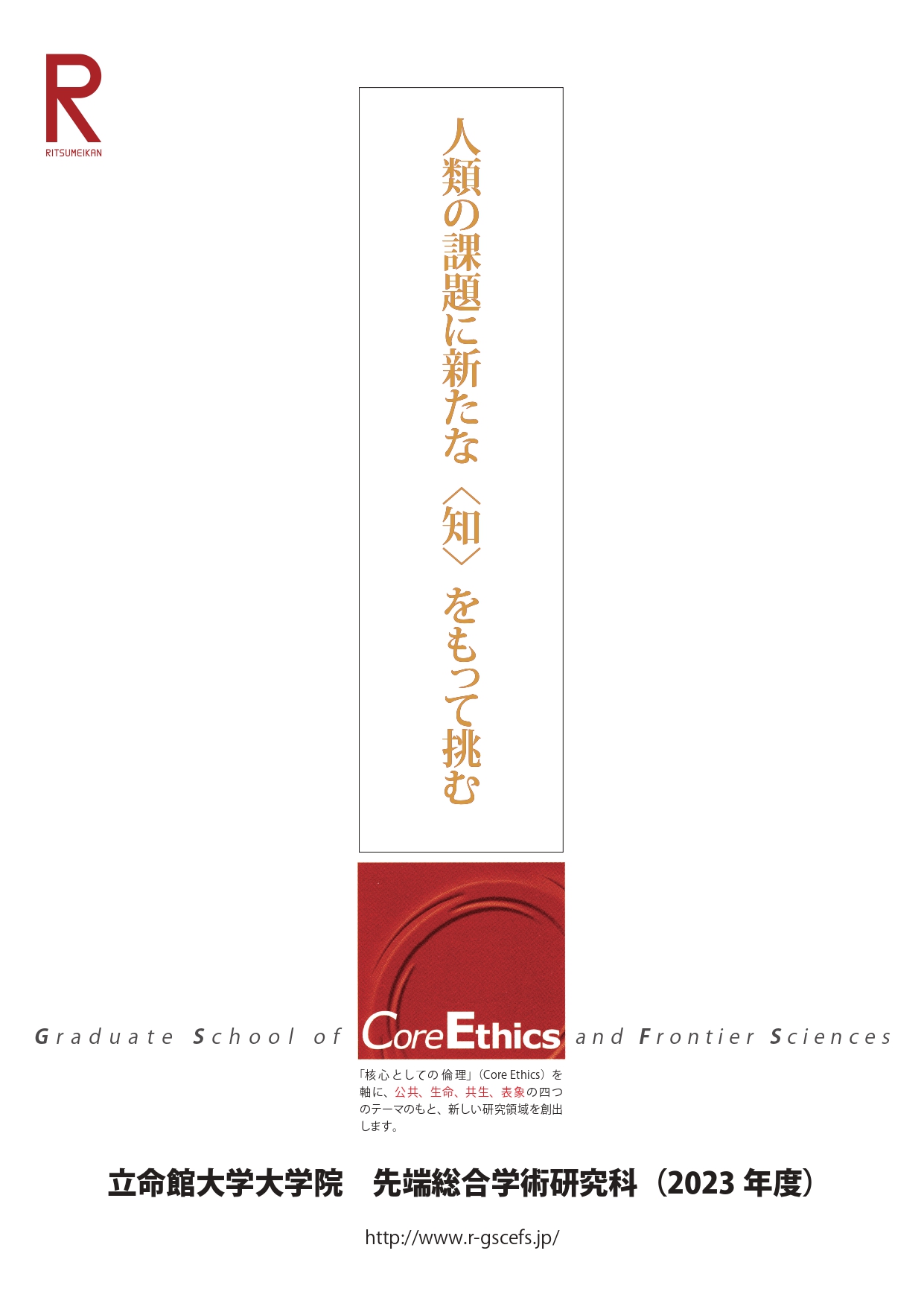

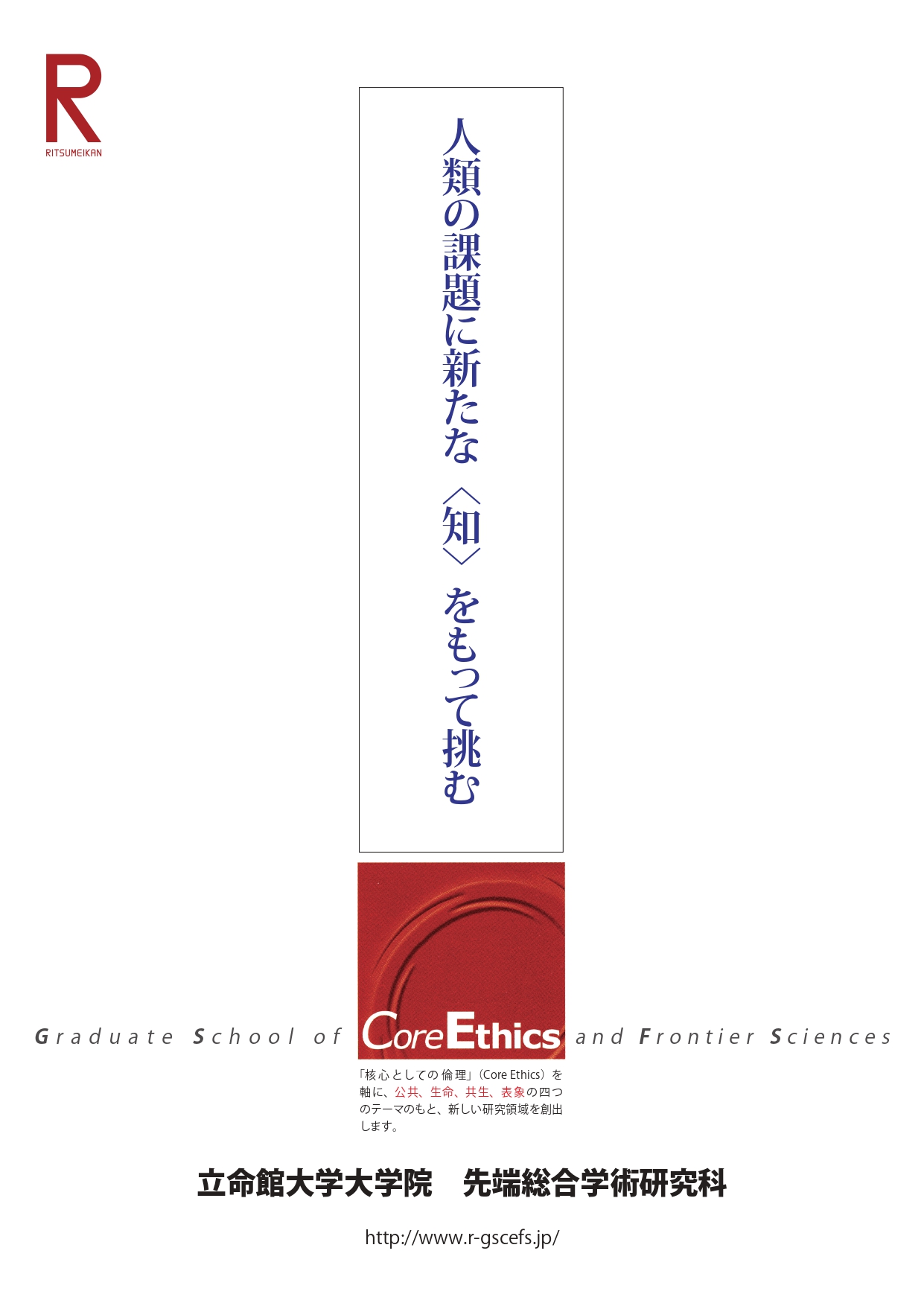
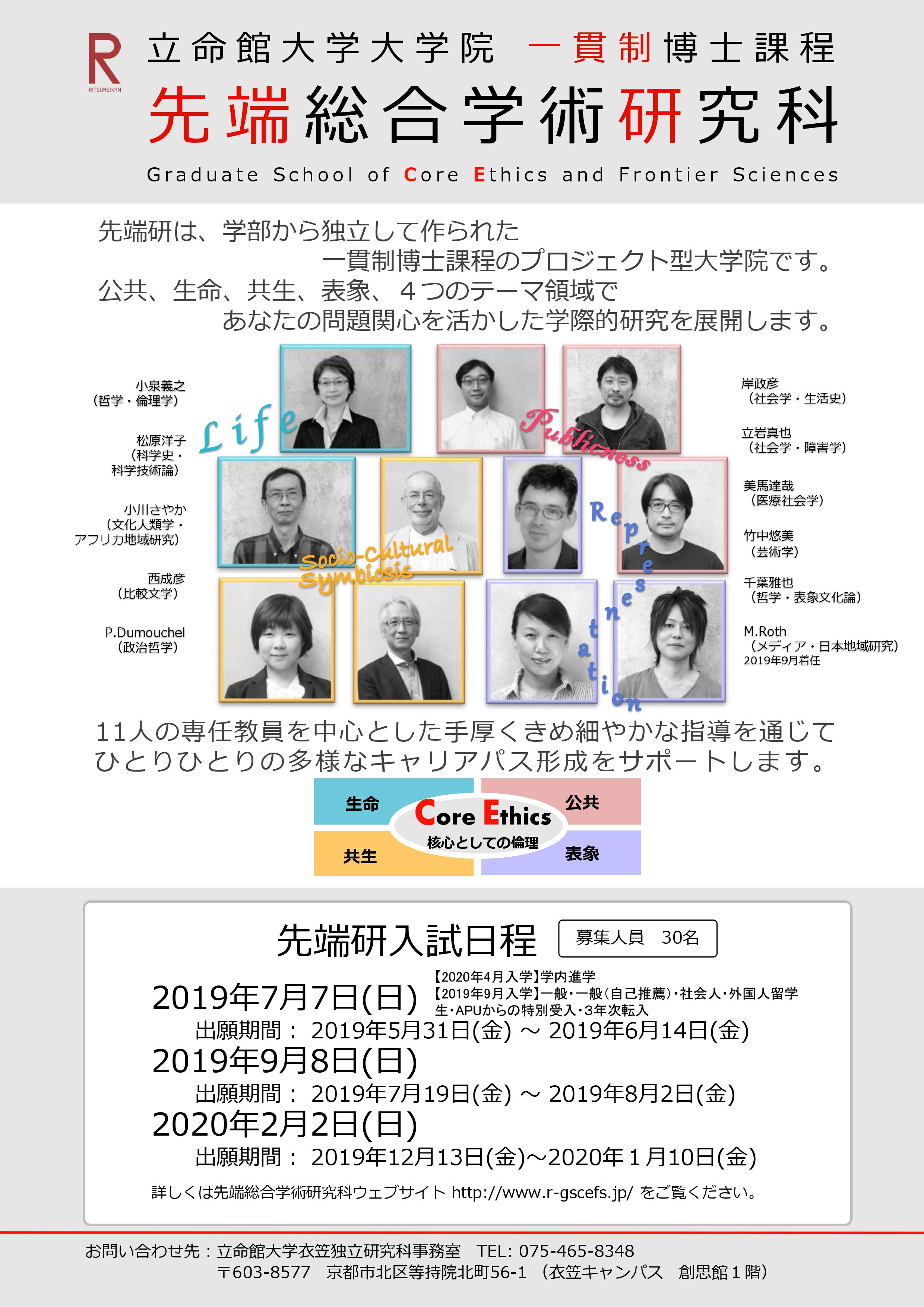

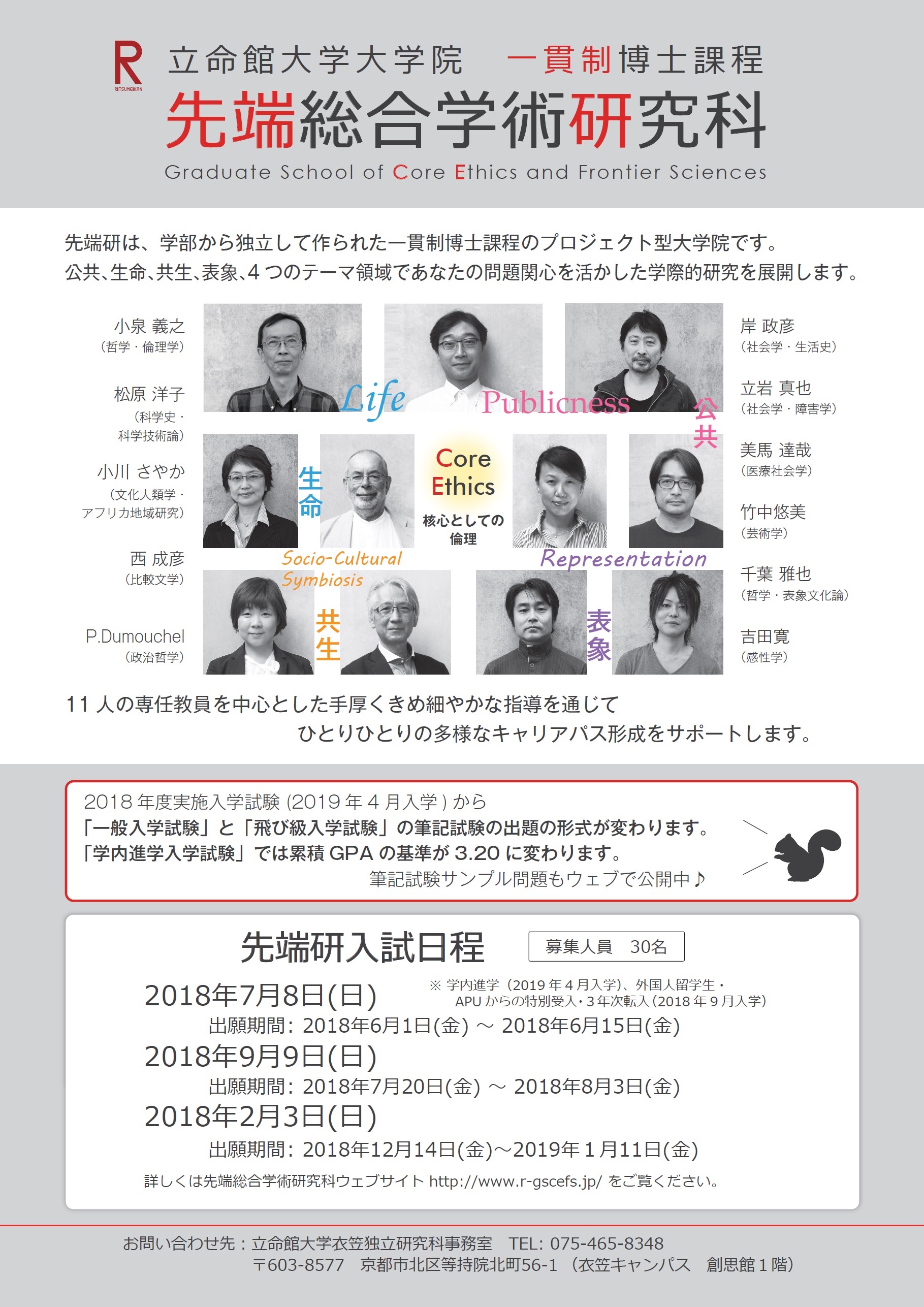

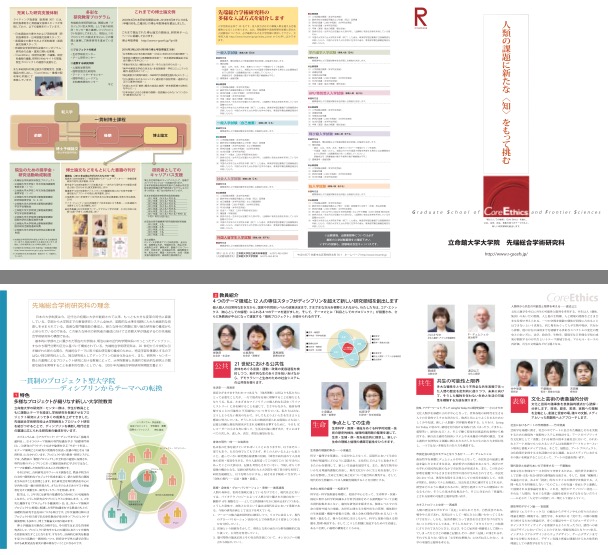
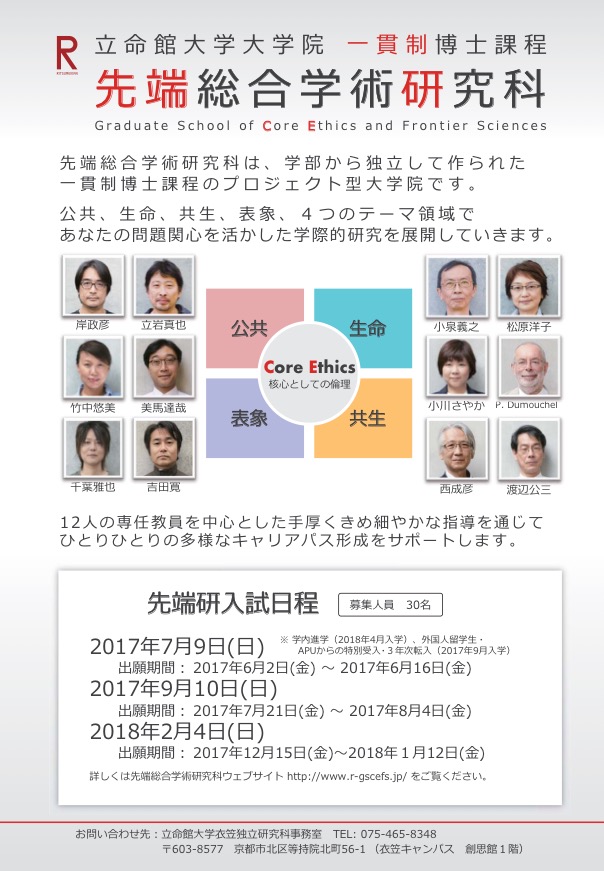
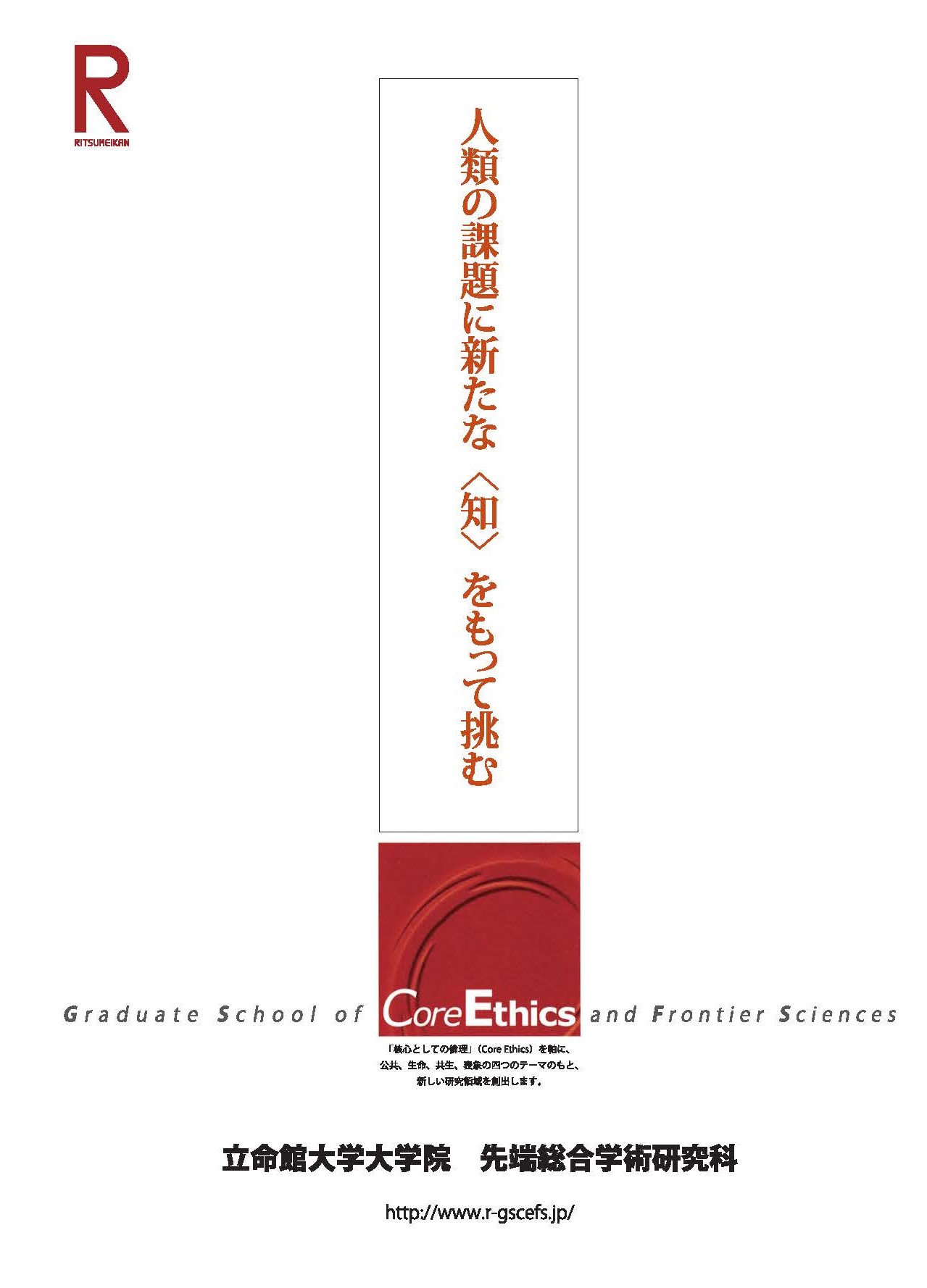
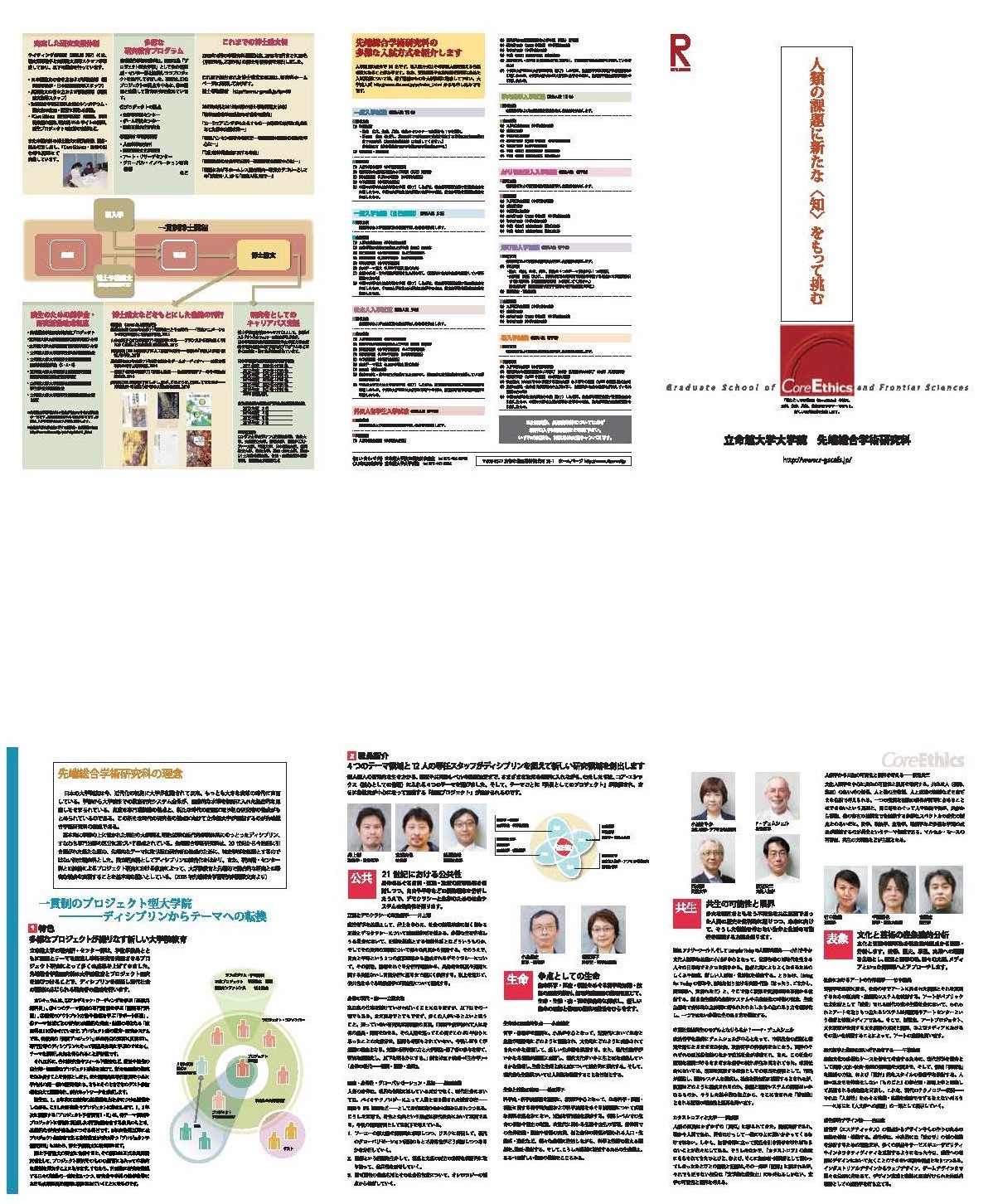
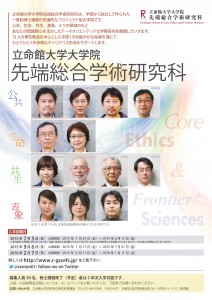
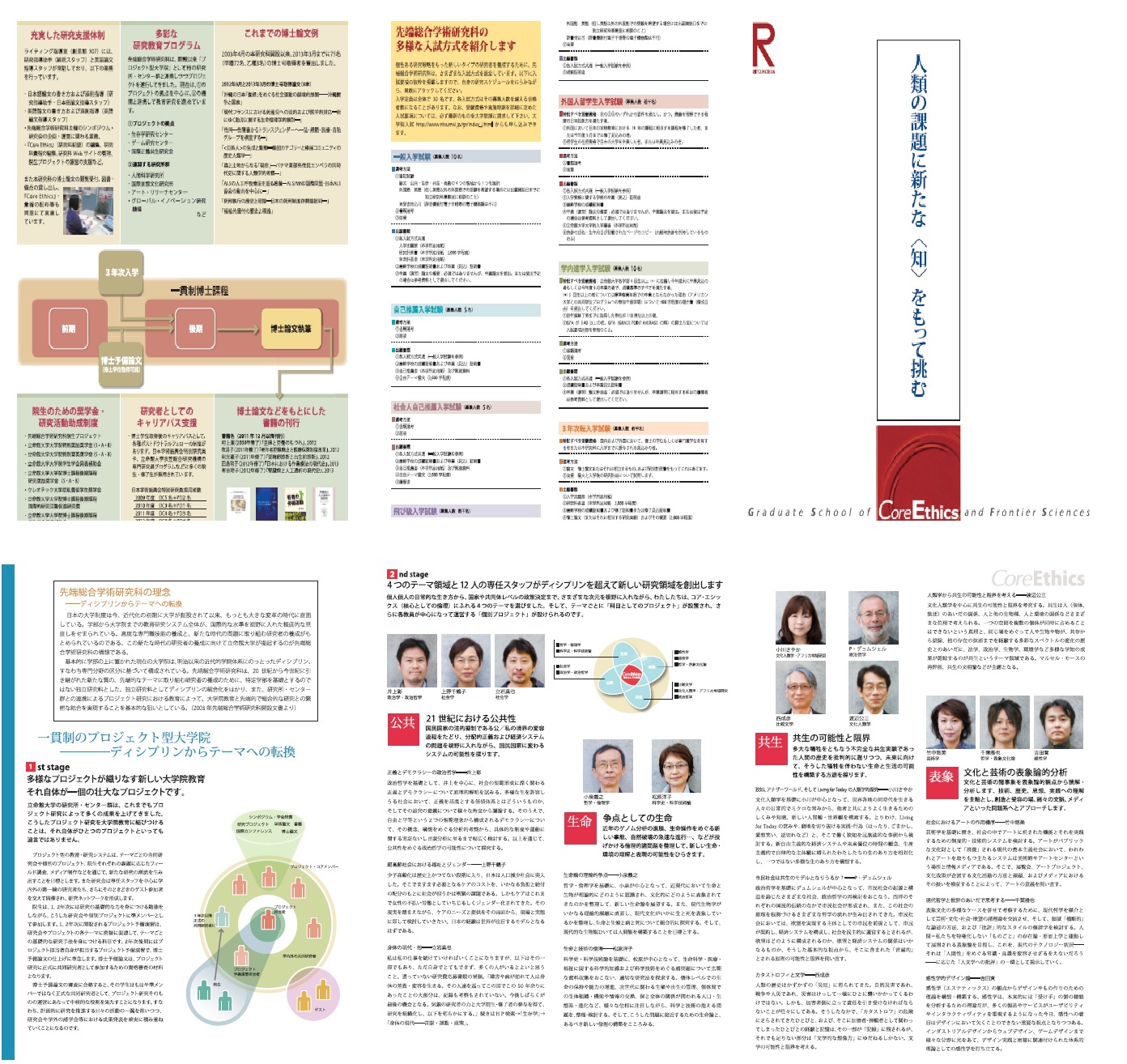
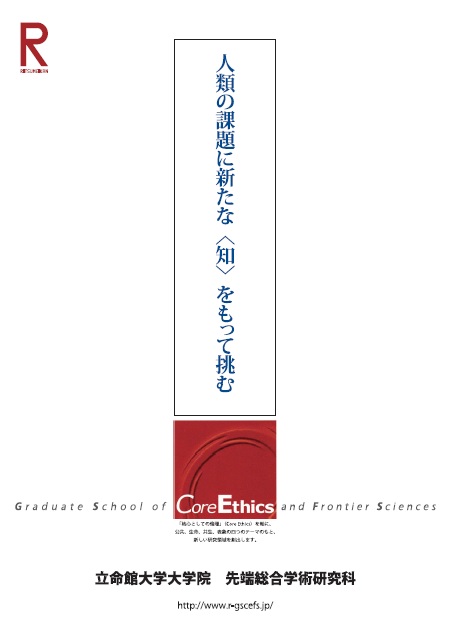
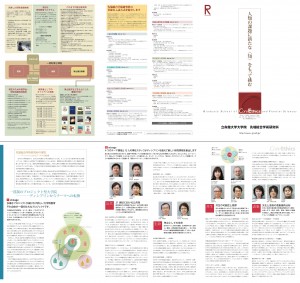
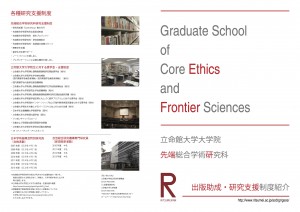
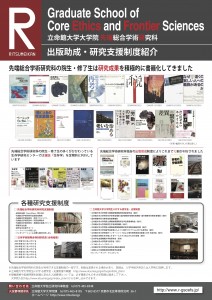
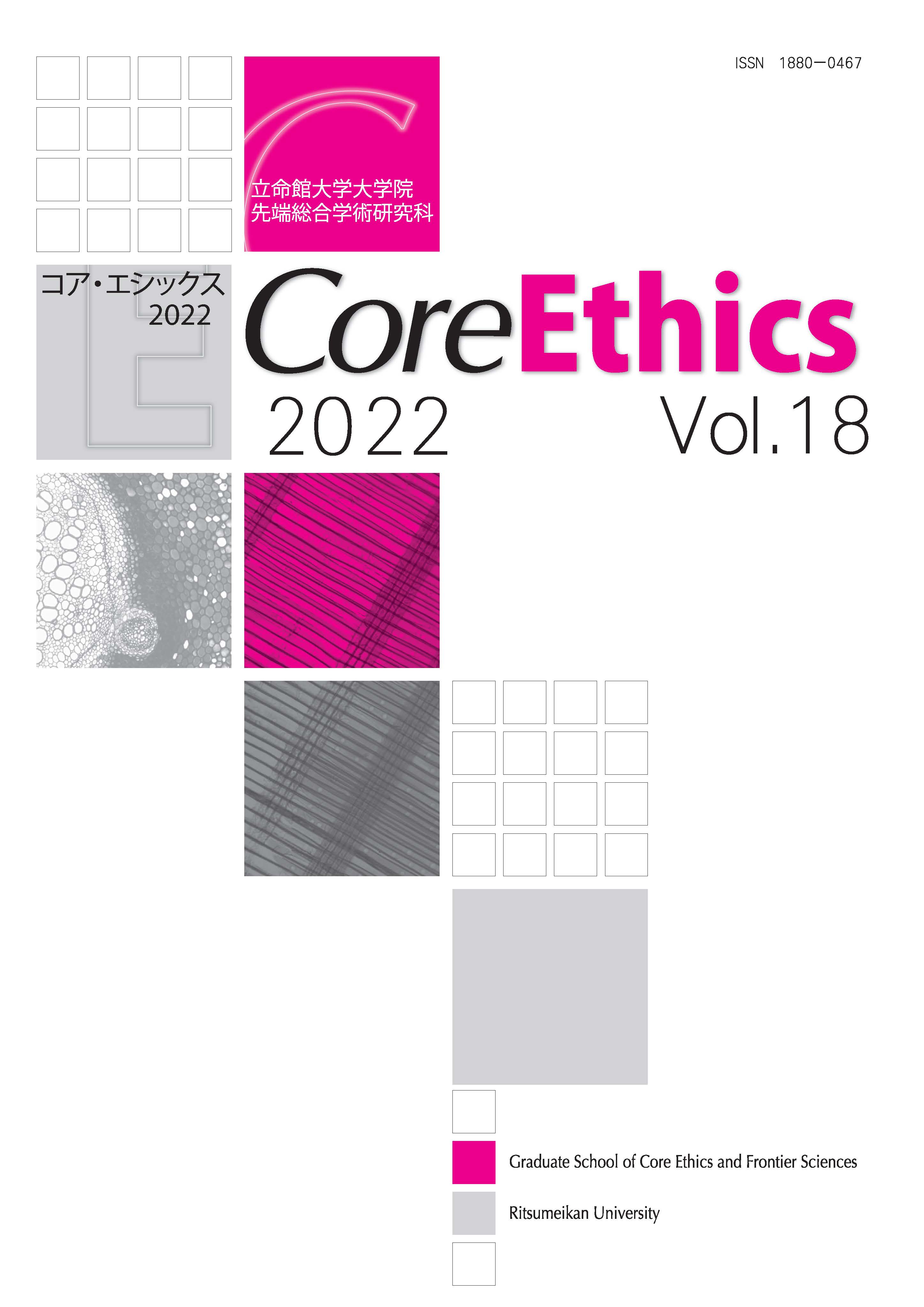

.jpg)
